入札公告には、入札保証金や契約保証金に関する記載があり、多くの企業がその内容について疑問を抱くことが少なくありません。
入札保証金は、落札後に契約を確実に締結するための保証として、一方の契約保証金は、契約内容を履行するための保証として求められます。
本記事では、これら2つの保証金の詳細や免除となる要件、入札保証金に代わる担保について解説します。
最後には、入札保証金についてよくある質問と回答を紹介していますので、疑問や不安点を解消して入札の準備を進めましょう。
▶ 入札で新しい販路を開拓したい企業の方へ
のべ3,000社以上の相談実績と、NJSS運営16年以上の知見で
入札参入から落札ノウハウまで、入札アドバイザーがサポートします。
▶ 調達業務を効率化したい発注機関担当者の方へ
全国の自治体をはじめ9,000以上の官公庁が公示する調達情報の検索・閲覧が可能。
情報収集・仕様書作成・業者選定など日々の業務を大幅に効率化できます。
入札保証金と契約保証金の違いとは
入札に関連するの保証金には、以下の2種類があります。
| 入札保証金 | 契約締結の保証を求める保証金 |
| 契約保証金 | 契約履行の保証を求める保証金 |
2つは納めるタイミングや目的が異なるため、次項で詳しく見ていきましょう。
入札保証金とは
入札保証金とは、発注機関が落札者に対して「契約締結の保証」を求めるために、入札参加者が納める保証金です。
落札したにもかかわらず契約に至らない場合、それまでに発注機関が費やした経費や時間に損失が生じます。また入札の再実施が必要となるため、発注機関の計画にもマイナスの影響を与えかねません。
そのため発注機関は入札参加者に対して、落札後の契約辞退を防止する目的で、一定の保証金の納付を求めているのです。
なお落札者が契約を辞退するケースとしては、次のような状況が考えられます。
- 採算が取れない低価格で誤って入札してしまった
- 落札後に予定していた技術者を配置できなくなった
正当な理由なく契約締結をしなかった場合、入札保証金は国庫に帰属され、没収されます。
それだけでなく、競争参加資格が取消になる罰則が科されるケースもあるため、ペナルティを避けるためにも入札は慎重に行いましょう。
入札保証金の実態
過去には入札保証金を求める地方自治体が多数でしたが、近年では入札者の負担を減らす目的で「免除」されるケースが増えています。
とくに、過去の実績や信用調査の結果を通過しているなど、一定の基準を満たす企業に対しては、保証金不要とする地方自治体もあります。
保証金は現金納付が原則ですが、代替手段として「金融機関の保証」や「保証会社の利用」を認めるケースが増加し、直接現金を納付するケースは減少しているのが実態です。
ただし、大規模な建設工事やインフラ工事の場合、保証金を求められる一方、小規模な物品購入や役務提供では免除されるなどと、案件の種類により取り扱いは異なります。
現在では、特に物品や役務に関する案件では「入札保証金なし」の案件が増えており、保証金が必要な案件は少数派といえます。
契約保証金とは
契約保証金は、落札者が契約を履行しない場合に発生する損害に備えて、発注機関が落札者に求める保証金です。
通常、保証金は契約締結の納付が原則ですが、事前に納付した入札保証金が充当される場合もあります。
なお、契約保証金は、契約の状況に応じて以下のように扱われます。
- 契約金額が増額した場合は追加納付
- 契約金額が減額した場合は減額または返還
- 適切に契約を履行した場合は返還
- 契約を履行できなかった場合は没収
契約を履行できなかった場合、契約不履行により損害賠償の請求や違約金が発生するケースがあるため、入札の段階で自社で履行能力を精査することが大切です。
契約保証金の実態
契約保証金は、大規模工事や高額案件では、契約保証金が定められているケースが多くなっています。
とくに、国や地方自治体の建設工事、インフラ整備案件では、契約保証金が規定されるケースが一般的です。ただし物品購入や役務提供などの小規模案件では、契約保証金が不要となる場合も増加傾向にあります。
また、近年では、一定の条件を満たした信用のある企業に対し、契約保証金を免除したり、保証会社の利用で代替手段を認めるケースも増えています。
契約保証金が求められる案件は、入札保証金と比較して一定数あるものの、免除されるケースの増加により、全体的に減少傾向にあるといえるでしょう。
保証金はいくらから必要なのか
入札保証金は「入札金額の5%以上」、契約保証金は「契約金額の10%以上」と、会計法および地方自治法で定められています。
以下は、入札保証金と契約保証金の詳細になりますので、ご参考ください。
| 入札保証金 | 契約保証金 | |
| 納付金額 | 入札金額の5%以上 | 契約金額の10%以上 |
| 納付期限 | 入札公告に定める提出期限内 | 契約予定日以前 |
| 納付方法 | 現金と有価証券 | 現金と有価証券 |
| 払込方法 | 振込やクレジットカード ※案件により異なる |
振込やクレジットカード ※案件により異なる |
| 保証金の取り扱い | ・落札者は契約保証金の一部に充当されるのが一般的 ・未落札者には返還 ・落札後の契約辞退は没収 |
・履行した場合は返還 ・不履行の場合は没収 ・契約金額の増額は追納 ・契約金額の減額は返還または減額 |
どちらの保証金も納付できない場合、入札辞退やペナルティの対象となるリスクがあるため、事前に予算の確保が必要です。
参考:
e-Gov法定検索「会計法第二十九条の四」
e-Gov法定検索「会計法第二十九条の九」
入札保証金や契約保証金が免除になる条件
入札保証金や契約保証金は、公正な取引を確保し契約不履行を防ぐ目的で設定されていますが、特定の条件を満たす場合は保証金が免除されることがあります。
免除の条件は発注機関や自治体によって異なりますが、主に過去の取引実績や担保の提供、保険契約の締結、小規模契約であるかどうかなどが考慮されます。ここからは、入札保証金と契約保証金それぞれの免除条件について詳しく解説します。
入札保証金の免除条件
入札保証金が免除される場合、下記のようなケースが挙げられます。
①入札保証保険契約の締結
入札参加者が保険会社と入札保証保険契約を締結しその証書を提出した場合、入札保証金の納付が免除されることがあります。
こちらは予算決算及び会計令(予決令)第77条により定められている既定です。
予決令第77条
契約担当官等は、会計法第29条の4第1項ただし書の規定により、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。1 一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に国を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。2 第72第1項の資格を有する者による一般競争に付する場合において、落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。
②契約保証の予約
銀行や保証事業会社と契約保証の予約を締結し、その証明書を提出した場合も入札保証金が免除されるケースがあります。
③過去の契約履行実績
過去2年間に国や地方公共団体と同種・同規模の契約を複数回誠実に履行した実績がある場合、入札保証金の免除対象となることがあります。
契約保証金の免除条件
契約保証金が免除される場合、下記のようなケースが挙げられます。
①確実な担保の提供
入札保証金と同様に、契約者が銀行の保証や保険会社との履行保証保険契約など、確実な担保を提供する場合、契約保証金の納付が免除されることがあります。
以下は長野県の財務規則で定められている内容です。過去2年以内にほぼ同じ契約を2回以上履行していると契約保証金の納付が免除になることがわかります。
財務規則第143条第3号
契約人が、過去2年間に国若しくは地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと認められるとき。
②小規模契約
地方公共団体によっては、契約金額が一定額未満の場合契約保証金が免除されるケースもあります。
茨城県牛久市の例では、設計金額が500万円以上の建設工事及びコンサルタント業務に係る契約に関して契約保証金を必要とすると定められています。
参照:契約保証金の取扱いについて | 牛久市公式ホームページ
落札出来なかった場合は返還される
落札に至らなかった場合、入札保証金は入札期間終了日以降に、指定口座へ返還されます。また、入札保証金を納付したあとに入札を辞退した場合も、同様に返還対象となりますす。
なお、返還時期は案件や発注機関によって異なるため、具体的な返還スケジュールについては発注機関に問い合わせしましょう。
入札保証金や契約保証金の支払い方法(納付方法)
入札保証金や契約保証金の支払い方法(納付方法)には、主に現金納付や銀行振込、クレジットカード決済、有価証券などがあります。現金納付は指定の金融機関で振込用紙を使用し、銀行振込は発注機関の指定口座へ送金します。一部の公的機関ではクレジットカード決済も可能。
また、国債や地方債などの有価証券を担保として提供する方法もあります。具体的な納付方法は案件ごとに異なるため、募集要項や各機関の指示を確認しましょう。
入札保証金に代わる入札保証
入札保証金の納付の代わりに、入札保証として発注機関から認められている方法があります。
| 入札ボンド | 金融機関や保証会社が提供する入札保証 |
| 入札保証金に代わる担保 | 会計法ならびに、予算決算及び会計令で認められている、入札保証方法 |
次項で2つについて詳しく解説します。
入札ボンド
入札ボンドとは、金融機関や保証会社が公共工事の入札参加者に対して、審査や与信調査を経て提供する契約保証です。
入札保証金の免除が受けられる入札ボンドには、以下の4種類があります。
| 入札ボンドの種類 | 特徴 |
| 保険会社の入札保証保険 | ・保険会社が提供する入札保証の保険 ・保険契約を結び、保証額に応じて保険料を支払うことで保証を受けられる |
| 金融機関の履行保証予約 | ・金融機関が提供する入札保証 ・落札後に契約保証へ申し込んだ際、保証書の交付を約束すること |
| 保証事業会社の契約保証予約 | ・保証事業会社が提供する入札保証 ・落札後に契約保証へ申し込んだ際、保証書の交付を約束すること |
| 金融機関の入札保証 | ・金融機関の信用のもと発行される入札保証 ・企業の信用審査で保証の可否や金額が決定 |
なお入札ボンドを利用する際、金融機関や保証会社による審査が行われ、申請が承認されないケースがあります。
理由は、金融機関や保証会社で一定の基準を設けることで、不正業者の応札を防止して適切な契約履行を目的としているからです。
企業の経営状況や工事施工能力が考慮されるため、自社の財務状況や信用力を確認したうえで、適切な入札保証の手続きを進めましょう。
入札保証金に代わる担保
入札保証金や入札ボンドにくわえ、会計法ならびに、予算決算及び会計令で認められた担保を提供することで、入札保証金を代替することも可能です。
以下は、代表的な担保の例です。
- 国債
- 政府の保証のある債券
- 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券
- 銀行が振り出し、または支払保証をした小切手
- その他確実と認められる担保で財務大臣の定めるもの(公社債、社債、地方債、定期預金債権など)
入札保証金に代わる担保として認められる資産の種類や要件は、発注機関により規定が異なるため、事前に確認しておきましょう。
入札保証金に関するよくある質問
次項では、入札保証金に関するよくある質問に回答します。
- 入札保証金と契約保証金の違いは?
- 入札保証金振込証明書とはなに?
不安や疑問を解消してから、入札の準備に取り掛かりましょう。
入札保証金と契約保証金の違いは?
入札保証金と契約保証金はどちらも発注機関が求める保証金ですが、目的や納付タイミングが異なります。
- 入札保証金:落札後の契約締結を保証するため、入札参加者が入札前に納めるもの
- 契約保証金:契約内容の履行を保証するため、落札者が契約前に納めるもの
2つの主な違いは以下のとおりです。
| 入札保証金 | 契約保証金 | |
| 納める対象者 | 入札参加者 | 落札者 |
| 保証内容 | 契約締結の履行 | 契約内容の履行 |
| 納める時期 | 入札参加前 | 契約前 |
| 納める金額 | 見積金額の5%以上 | 契約金額の10%以上 |
どちらの保証金も納められない場合、入札辞退もしくはペナルティにつながるリスクがあるため、事前に予算の確保が必要です。
なお、発注機関によっては免除される案件があるため、事前に入札公告を確認しておきましょう。
入札保証金振込証明書とはなに?
入札保証金振込証明書とは、入札参加者が入札保証金を納付したことを証明する書類です。
とくに競売入札では公共工事の入札と異なる書類を準備する必要があり、そのひとつが「入札保証金振込証明書」です。証明書には、保証金の振込明細書を貼り付けて提出します。
入札保証金振込証明書は、厚生労働省や地方自治体のHPからダウンロードできるほか、物件を管轄する地方裁判所でも交付を受けられます。
なお、入札保証金振込証明書は公共工事の入札には直接関係がない書類となりますので、基本的に準備は不要です。
受付中の入札案件や過去の案件情報を探すなら「NJSS」
入札案件は、発注機関のHPや案件情報サービスで検索して探すのが一般的です。しかし情報が膨大で、自社に適した案件を探すのが困難、と感じることもあるのではないでしょうか。
そのようなときに役立つのが、「入札情報速報サービス NJSS」です。
NJSSは、全国の官公庁や地方自治体、公共機関が発注する入札情報を網羅的に収集し、企業が必要な情報を迅速に入手できるサービスです。
- 全国8,800以上の発注機関の入札案件を収集
- 年間180万件以上の入札案件
- 累計1,800万件以上の落札情報
- 入札案件、落札案件、発注機関を検索
- 万全なフォロー体制
- 競合企業の動向調査
このような機能の活用により、情報収集にかかる時間を大幅に削減できます。効率的に入札チャンスをつかむなら、NJSSの活用が最適です。
まずは、無料トライアルで、NJSSの便利さを実感してみてはいかがでしょうか。
入札保証金は現金以外にも種類がある
入札保証金は、入札参加時に納付する保証金ですが、会計法や地方自治法の規定により免除されるケースもあります。
また、入札保証金は現金だけでなく、保険会社の入札保証保険や金融機関の入札保証など、さまざまな形で提供されるため、自社に適した方法を選択できます。
具体的な保証金の要件や免除の可否については、各入札の公告に詳細が記載されています。入札に参加する前に必ず確認し、適切な準備を進めましょう。
▶ 入札で新しい販路を開拓したい企業の方へ
のべ3,000社以上の相談実績と、NJSS運営16年以上の知見で
入札参入から落札ノウハウまで、入札アドバイザーがサポートします。
▶ 調達業務を効率化したい発注機関担当者の方へ
全国の自治体をはじめ9,000以上の官公庁が公示する調達情報の検索・閲覧が可能。
情報収集・仕様書作成・業者選定など日々の業務を大幅に効率化できます。






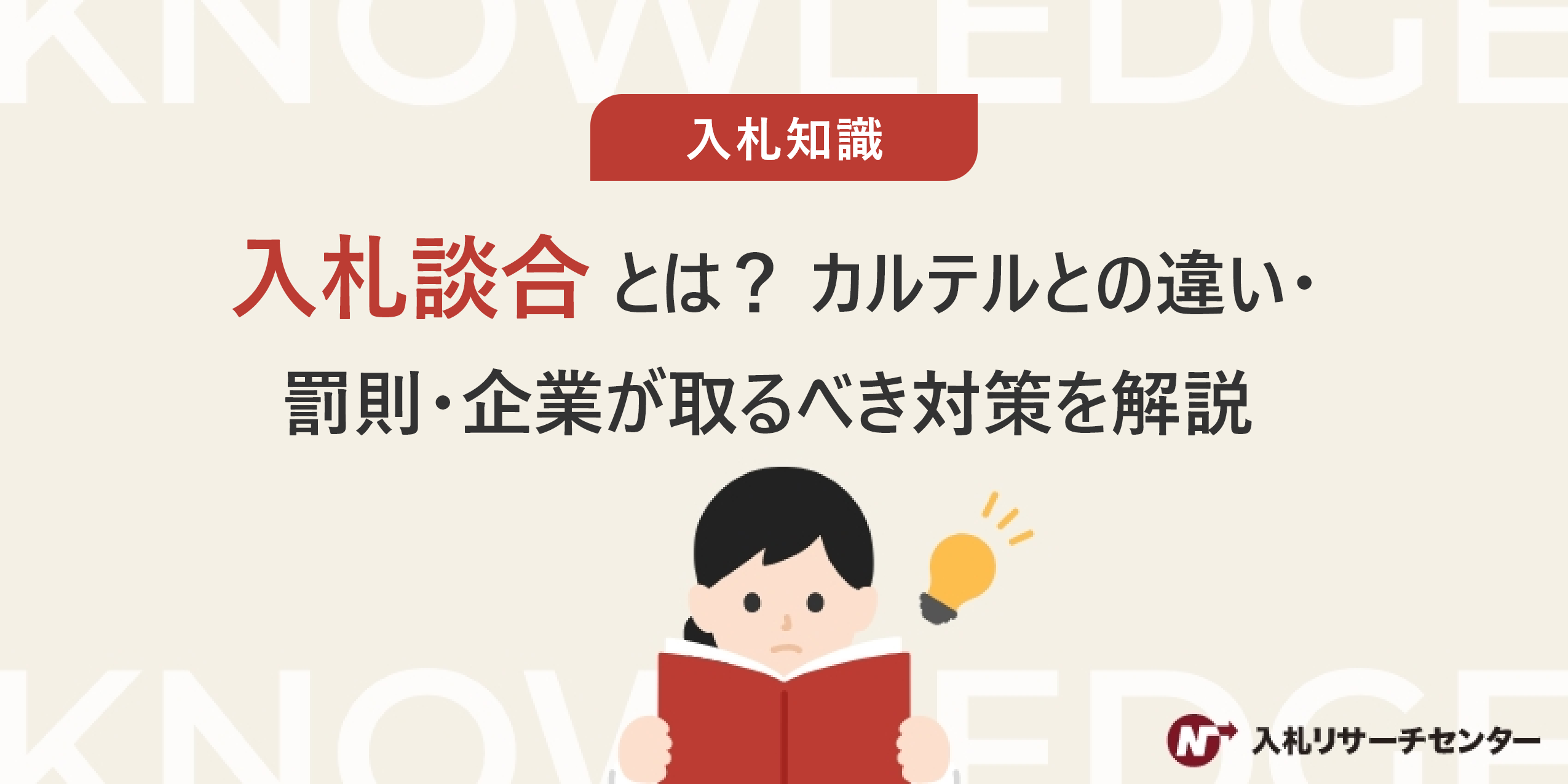
アイキャッチ.png)
.png)
.png)


