近年は建設費や人件費の高騰、人手不足などの要因から、全国的に入札不調が増加しています。入札不調が続くと、工事の遅延や予算の膨張、地域経済への悪影響が懸念されます。
落札するためには、不調案件を見極め勝てる案件に集中することが肝心です。しかし、そのためには入札不調の原因を正しく理解し、適切な対策を講じなくてはなりません。
本記事では、入札不調と入札不落の違いや具体的なケース、対策などを解説します。
入札アカデミー(運営:株式会社うるる)では、入札案件への参加数を増やしていきたい企業様向けの無料相談を承っております。
のべ3,000社以上のお客様に相談いただき、好評をいただいております。入札情報サービスNJSSを16年以上運営してきた経験から、入札案件への参加にあたってのアドバイスが可能です。
ご相談は無料となりますので、ぜひお問い合わせください。
入札不調とは?
入札不調とは、入札公告に対して入札参加者がいない状態、または条件を満たす業者がいないために、契約相手が決まらない状態を指します。
入札への参加がない状況はそう珍しいことではなく、大規模なプロジェクトでも入札不調に陥ることはあり得ます。
実際、過去にも大阪関西万博の入札不調がニュースで大きく取り上げられました。
入札不調が発生した場合、発注機関は入札条件の見直しや、再公告などの対応が必要となります。発注機関にとっては、事業計画の遅延や事務手続きの増加といった大きな負担となるケースが多いでしょう。
参考:沖縄タイムス/縄県の大型MICE施設、参加表明の事業者ゼロ きょう18日が期限、入札不調の可能性も 2029年の開業に遅れも
参考:日経BP/万博の入札不落・不調は「2024年問題」の予兆か、炎上リスク回避か
入札不調となる具体的なケース
入札不調が発生しやすいのは、以下のようなケースです。
- 発注者の予定価格が市場の実勢価格より大きく下回っている
- 条件が厳しすぎて、対応可能な企業が極端に限られる
- 人手不足や資材高騰により、企業に受注の余力がない
こうした構造的な要因に加え、入札参加者側の事情も影響します。たとえば、入札公告の情報に気づけなかった、公告内容がわかりにくかったといった情報不足、あるいは参加資格のハードルが高く技術力や実績が条件を満たさないケースも多く見られます。
また、履行期間が短すぎる、ロットが大きすぎる、必要な人員や機材が確保できないといったリソース面の課題も深刻です。さらに、予定価格が安すぎて採算が取れないと判断されることもあります。
実際に、大型病院や庁舎建設では、予定価格と実勢価格の差から複数回の不調が起きています。不調を防ぐには、企業が参加しやすい条件や価格設定、情報発信の工夫が不可欠です。
入札不落との違い
入札不調と入札不落は、どちらも落札者が決まらない点では同様です。しかし、原因や対応方法が異なります。下表で比較してみましょう。
| 項目 | 入札不調 | 入札不落 |
| 特徴 | 入札に参加する事業者が存在しないため、入札が成り立たない状態 | 入札参加者は存在するものの、条件が合わず落札に至らない状態 |
| 主な原因 | 情報が届いていない、条件が厳しい、人手が足りないなど | 金額が合わない、内容が求められる基準に届いていない |
| 法的根拠 | 自治法施行令167条の2 (入札者なしの場合) |
自治法施行令167条の2 (落札者が決まらない場合) |
入札不調は関心を持たれる案件設計ができていない状態であるのに対し、入札不落は参加はあったが発注側の条件と合わなかった状態といえます。
それぞれに対する対応策も異なるため、原因を正しく特定することが、的確な再入札や契約手続きへの第一歩となります。
入札不調が増加する背景とは
近年、入札不調は全国的に増加傾向にありますが、国や自治体の制度改善によって、一部では改善の兆しも見られます。令和4年度の国土交通省の資料によると、不調・不落の発生率は11.7%と、過去数年に比べてやや改善が進んでいます。
ただし、機械設備や建築関連の工事では依然として不調率が30%を超えており、特定分野では深刻な状況が続いているのも実情です。
以下では、入札不調が増加する主な背景を解説します。
- 建設費や資材の価格高騰
- 建設業界の人手不足が深刻化
- 予定価格と実勢価格のズレ
- 入札制度のルールが時代に合っていない
それぞれ詳しく見ていきましょう。
参考:国土交通省関東地方整備局|令和5年度入札・契約、総合評価の実施方針
建設費や資材の価格高騰
近年の入札不調の背景には、建設資材価格の高騰が大きく影響しています。2021年以降のウッドショックやアイアンショックの影響によって、建設資材物価指数は2024年までに約31%上昇しました。
現在も鋼材・木材・生コンクリートなどの主要資材は高値圏で推移しており、採算確保が困難と判断した企業が応札を見送るケースが全国的に増えています。大阪・関西万博関連のテーマ館や大催事場においても、資材費の上昇や工事の難易度が影響し、入札不成立や再公告が相次ぎました。
とくに機械設備工事や建築一式工事は、資材コストの比率が高いため価格変動の影響を受けやすく、入札を避ける動きが顕著です。
このような事態を防ぐには、市場実勢を反映した予定価格の設定が不可欠です。企業が安心して応札できる環境整備が求められるでしょう。
参考:一般社団法人日本建設業連合会|建設工事を発注する民間事業者・施主の皆様に対するお願い
以下の記事では、入札と応札の違いについてわかりやすく解説していますので、あわせて参考にしてください。
関連記事:入札と応札の違いは?入札方法や流れ、応札者がいない場合について解説
建設業界の人手不足が深刻化
建設業界では人手不足が長期的な課題となっており、2025年には団塊世代の大量退職によって、技能労働者の確保がさらに難しくなると見込まれています。若年層の入職は依然として低調で、業界全体の高齢化が進行している状況です。
2024年4月からは「働き方改革関連法」にもとづく時間外労働の上限規制が、建設業にも適用されました。従来のような長時間労働による工程調整が難しくなり、短い工期の案件では対応が困難となっています。
国土交通省の発表によれば、2025年度の公共工事設計労務単価は全国平均で24,852円と過去最高水準に達しています。しかし、依然として他産業との賃金差があり、人材確保につながるかは不透明です。
とくに都市部では、技術者や作業員の確保競争が激化しており、応札を見送る企業が増加しています。こうした状況への対応としては、現実的な工期設定、ICTや建設DXの導入支援などが求められます。
参考
国土交通省|令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について
予定価格と実勢価格のズレ
入札不調の大きな要因のひとつが、発注者が設定する予定価格と、企業が見積もる市場価格(実勢価格)との乖離です。とくに、設計金額を一律に削減する歩切り(ぶぎり)が残る自治体では、企業が採算を見込めず応札を見送る例が増えています。
歩切りとは、設計上の積算価格から根拠なく数%から1割程度を削る手法で、適正な契約価格を阻害するものです。国土交通省も、公共工事品質確保法にもとづき、歩切りの廃止を制度運用指針で求めています。
また、過去の物価水準を前提とした積算では、近年のコスト上昇に対応できず、企業が赤字リスクを懸念して応札を見送る要因となっています。こうした状況には、次のような対応が必要です。
- 歩切りの撤廃
- 市場価格を反映した積算の徹底
- 積算基準の定期的な見直し
これらの見直しによって、企業が実情に即した価格で応札しやすくなり、入札の成立率や工事の安定的な実施につながります。
参考:国土交通省|「歩切り」の廃止による予定価格の適正な設定について
入札制度のルールが時代に合っていない
現在の入札制度には、企業の参入を阻む構造的な課題があります。とくに中小企業にとっては、手続きの煩雑さや過度に厳しい参加条件が大きな負担となっており、入札を見送るケースが後を絶ちません。
また、「1社のみの応札は無効」とする自治体もあり、参加をためらう企業が増えています。こうした制度面での問題を解消するには、下記のような対応が必要です。
- 手続きの簡素化
- 電子入札の導入・拡充
- 総合評価方式やプロポーザル方式など、多様な契約方法の導入
制度の改善により、企業の参加意欲を高め、地域の施工力を活かした安定的な工事実施が可能になるでしょう。
入札不調が引き起こす主な4つの影響
公共工事で入札不調が発生すると、おもに下記の影響があるとされています。
- 工事が進まず、公共インフラ整備が遅れる
- 再入札などで事業コストが膨らむ
- 地元企業の受注機会が減る
- 福祉・教育など住民サービスの提供が遅れる
詳しく見ていきましょう。
工事が進まず、公共インフラ整備が遅れる
入札不調が起こると、再入札の手続きや条件見直しに時間を要し、工事の着手が大幅に遅れるリスクがあります。道路や上下水道、病院などのインフラ整備が滞り、老朽化対策や災害復旧に支障をきたすおそれがあります。
仙台市役所本庁舎の空調設備工事では、2023年に2回の入札不調が発生し、契約成立は当初の予定から半年以上遅れました。こうした影響を抑えるには、以下の対応が求められます。
- 発注前の入念な市場調査
- 適正な予定価格の設定
- 現実的な工期の定義
- 段階発注・デザインビルド方式などの柔軟な発注手法
このような取り組みにより、公共事業の円滑な推進と、地域住民への影響の最小化が期待されます。
再入札などで事業コストが膨らむ
入札が不調に終わると、再度入札公告を出す費用や職員の手間が増え、工事費以外のコストも膨らみます。それだけでなく、資材価格の高騰に応じて再度予算を組みなおす必要が生じます。そのため、当初見込んだ額を大きく超過することも珍しくありません。
実際、2025年の大阪・関西万博関連工事では、テーマ館や大催事場などの施設で、予定価格を約45億円引き上げて再入札を実施したと報じられました。再入札ごとに物価変動や仮設工事費が積み重なり、総額が数十%膨れ上がる例もあります。
また、入札に参加する企業にとっても影響は大きく、下記のように、多くの労力が発生します。
- 入札公告の確認
- 仕様書の精読
- 積算・見積書の作成
入札が不成立となれば、それらの準備が無駄になるだけでなく、中小企業にとって、案件獲得機会の損失は経営に大きな影響を与えかねません。
こうした事態を避けるためには、初回入札の段階から市場価格を反映した予算設定と、十分な予備費の確保が不可欠です。
参考:朝日新聞|万博工事の入札で不成立の3件再入札へ予定価格は45億円増加
地元企業の受注機会が減る
入札不調が続くと、公共事業の遅延や中止が発生し、地元建設業者の受注機会が減少します。とくに地方では、公共事業への依存度が高く、発注の停滞が中小企業の経営に直結する深刻な問題です。
また、再入札で条件が厳しくなって発注ロットが拡大すると、大手企業しか対応できず、地域内での競争が失われる傾向があります。資材業者や運送業者などの関連業種にも影響が及ぶため、地域経済全体の活力低下につながります。
中小企業が参加しやすい発注規模の設定や、地域性に配慮した条件見直しが必要です。
福祉・教育など住民サービスの提供が遅れる
入札不調によって、下記のような公共施設の整備が遅れ、住民が受ける教育や医療などの基本サービスの質に影響が出ます。
- 学校
- 病院
- 福祉施設
- 図書館
たとえば学校の耐震工事が遅れると、安全面で不安が残る施設で学習を続けなければなりません。病院の建設が遅れると、医療体制の整備にも支障をきたします。
また入札不調・不落が頻発すると、入札市場全体の信頼性が低下し、健全な競争環境が阻害される懸念もあります。地域経済活動の停滞や企業の入札離れといった悪循環を避けるためにも、制度の見直しと実効性ある改善策の導入が不可欠です。
入札不調・入札不落が発生した場合の3つの対応策
入札不調や入札不落が発生した場合、発注機関は状況に応じて下記の対応をとります。
- 再入札公告
- 新規の入札公告
- 不落随契
なお、多くの発注機関では、入札は原則として3回までとしているため、なるべく初回で契約成立を目指す必要があります。
入札不調が発生した際の対処法については、以下の記事でも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
関連記事:入札不調の案件も再検討を
再入札公告
「再入札公告」とは、入札が成立しなかった際に、同じ案件について再び公告を行うことです。ただし、最初の条件がそのままでは再び不調に陥る可能性があります。そのため、下記の条件を見直したうえで、再度公告を出すのが一般的です。
- 予定価格
- 工期
- 仕様内容
再入札では、通常10日以上必要とされる公告期間を5日に短縮できるため、スピーディーに次の手続きへ進めます。
新規の入札公告
「新規の入札公告」は、元の入札案件から大きく条件を変更する必要がある場合に使われます。
下記のような変更がある場合には、新たに入札手続きをやりなおすことになります。
- 工事の内容が大幅に変わる
- 入札参加条件を緩和または厳格化する
- 予定価格を大きく修正する
必要な変更を反映させたうえで、あらためて入札手続きを行うことで、多くの入札参加者を集め、適切な競争環境を整えられます。
不落随契
「不落随契」とは、入札が不調または不落となった場合に、競争入札を行わず、特定の事業者と随意契約を締結する方法です。この手段は「入札不調・不落による随意契約」とも呼ばれることもあります。
たとえば、下記のようなケースで用いられます。
- 条件変更の必要がなく、再入札しても参加者が見込めない
- 発注を急ぐ必要があり、再公告にかける時間がない
- 特定分野の専門業者が少なく、競争が成立しにくい
ただし、随意契約は競争性がなく公平性に欠けるおそれがあるため、あくまでも適用は例外的です。発注機関には、契約内容や選定理由を文書で明確にし、第三者から見ても納得できる対応が求められます。
以下の記事では、随意契約について詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
関連記事:随意契約とは?一般競争入札との違いや契約までのポイントを解説!
入札で落札確度を上げる方法
ここでは、入札に参加する企業が落札率を上げる2つの方法を紹介します。
- 綿密な情報収集と分析を行う
- 精度の高い見積もりを作成する
競争入札において落札率を高めるためには、入念な準備と戦略的なアプローチが必要です。入札に参加する際は、綿密な計画を立てておきましょう。
綿密な情報収集と分析を行う
落札するためには、案件の徹底的な情報収集と分析が不可欠です。たとえば、下記のような情報は入札戦略を立てるうえで役立ちます。
- 過去の同様案件における落札金額や参加業者数
- 最低制限価格の有無と水準
- 発注機関の予算規模や重点施策
これらの情報は、入札情報サービスや、自治体・官庁の公式サイト、公告資料から収集できます。
また、説明会が開催される場合は、できるだけ参加して、少しでも多くの情報をキャッチしましょう。
精度の高い見積もりを作成する
正確な積算と見積もりは、落札を左右する重要な要素です。まずは、以下の費用を項目ごとに丁寧に見積もりましょう。
- 材料費
- 労務費(人件費)
- 外注費・機械使用料など
過去の類似案件の実績データを参考に、過不足のない積算を心がけることが大切です。
また、天候不順や資材価格の高騰などのリスクも考慮して、ある程度の余裕を持った価格設定も必要です。ただし、過剰なリスクを見込むと競争力が低下するデメリットがあるため、バランス感覚が求められます。
なお、細かい見積もりは複数人でチェックし、ミスや漏れを防ぎましょう。
入札不調の原因と対策を整理し、受注の精度を高めよう
入札不調の背景には、予定価格と実勢価格の乖離、過度な仕様要件など、複数の要因が絡んでいます。効果的な予防策として、適正な予定価格設定や柔軟な発注仕様への見直しなどがあげられます。
また、国や自治体では入札制度改革が進んでおり、透明性の向上や参加要件の緩和といった環境整備も進行中です。こうした動きを把握し、戦略的に対応することが、今後の受注獲得には欠かせないポイントです。
入札アカデミー(運営:株式会社うるる)では、入札案件への参加数を増やしていきたい企業様向けの無料相談を承っております。
のべ3,000社以上のお客様に相談いただき、好評をいただいております。入札情報サービスNJSSを16年以上運営してきた経験から、入札案件への参加にあたってのアドバイスが可能です。
ご相談は無料となりますので、ぜひお問い合わせください。





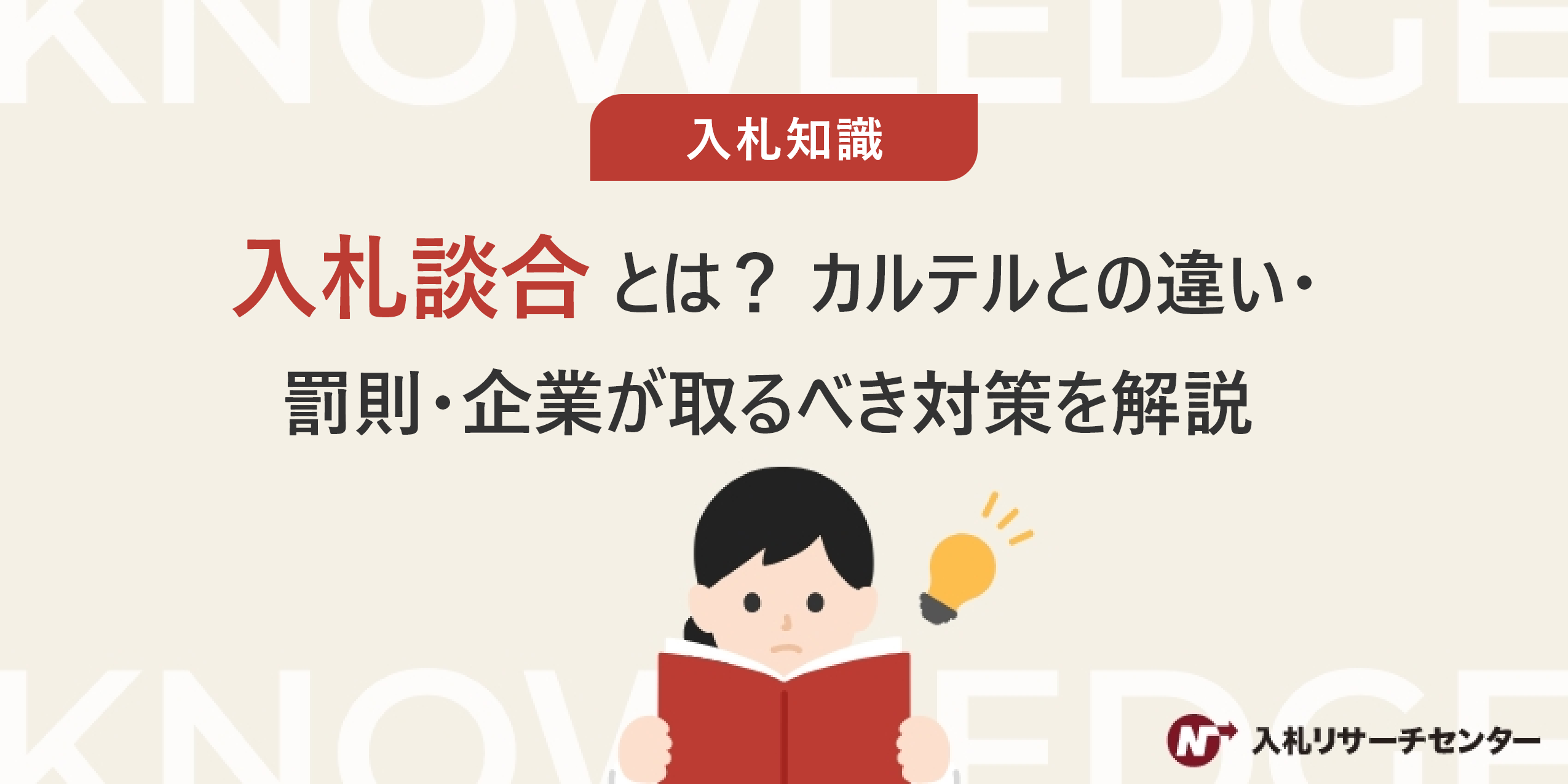

アイキャッチ.png)
.png)
.png)

