近年、医療現場ではさまざまな業務のデジタル化が進み、「電子カルテ」「医事会計」「部門システム」などの医療情報システムは、もはや病院運営の中核を担うインフラとなっています。
しかし、これらのシステムは導入後の運用期間が長期にわたることや、データ互換性の問題から「途中でベンダーを切り替える」ことが容易でなく、入札市場でも一部大手企業による寡占状態が長く続いていました。
ところが今、その構造が大きく変わろうとしています。
本記事では、この市場変化の背景を整理したうえで、企業が取るべき具体的なアクションについて解説します。
医療DXの本格始動─協議会発足と標準仕様策定の狙い
この変化の最大の引き金となっているのが、デジタル庁と厚生労働省が2025年7月に正式に発足させた「病院情報システム等の刷新に向けた協議会」です。
この協議会は、医療DX推進工程表に基づき、従来のオンプレミス型病院システムを刷新し、電子カルテやレセコン、部門システムを、モダン技術を活用したクラウド型システムへと統合的に移行する方針を進めています。
スケジュールとしては、2025年度中に標準仕様を取りまとめ、2026年度からは意欲ある事業者による開発が始まる予定です。初期の対象は、100〜200床程度の中小規模病院。地方都市の総合病院のように、一般的な急性期医療から回復期、慢性期医療まで幅広い機能を持つ病院が想定されています。今後、国立病院機構などでの試行導入を経て、大病院への展開も検討されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| スケジュール | 2025年度:標準仕様策定/2026年度:事業者による開発開始 |
| 対象病院(初期) | 病床規模:100~200床程度の中小規模病院 |
| 病院機能 | 地方都市の総合病院のように、一般的な急性期医療から回復期リハビリテーション、慢性期医療までの幅広い機能を有する |
| 対象部門システム | 薬剤部門システム、放射線部門システム、臨床検査部門システム、生理・手術・内視鏡・給食等 |
出典:病院情報システム等の刷新に向けた協議会の構成員が決定しました(デジタル庁 )
今後の入札市場に与える影響
この協議会には、旧来の大手IT企業だけでなく、クラウドネイティブ企業も多数参画しています。また、多くの自治体や病院に対して、補助金や診療報酬加算といった政策的な支援策も用意されているため、案件総量そのものが増加していくと見込まれます。つまり、これまでは限られた企業が限られた案件を受注していた市場が、以下の2つの要素によって大きく変化します。
- 新規プレイヤーの参入
- 案件総量の増加
この2つの要素が引き起こすのは、まさに『寡占状態から混戦状態へ』と移行するフェーズで、新たな競争環境が生まれようとしています。
大再編に備えるための3つの準備
市場が大きく変動する今こそ、過去の成功体験から脱却し、データに基づいた戦略的な意思決定が求められます。この激動の時代を乗り越えるために、企業が取るべき3つの準備を解説します。
① 競合企業の受注状況を定点観測する
「誰が、どの領域で、どの病院規模の案件を落札しているのか」を継続的に把握することで、自社の競争ポジションを明確にできます。過去実績の時系列変化を追うことで、競合の強み・弱み、そして市場からの撤退傾向なども見えてきます。
②新規参入企業の動きをウォッチする
クラウド企業は、電子カルテ単体や周辺システムなど“比較的入りやすい領域”から参入してくるケースが多く、将来的には関連領域にも横展開する傾向があります。初期段階でどの領域に入札・落札しているのかを把握しておくことで、「次にどこへ来るか」を見極められます。
③提案先と優先順位を見直す
競争構造が変化する局面では、“これまで勝てていた領域”が必ずしも最優先とは限りません。案件規模や地域、参入企業の動きを踏まえたうえで、どの案件にリソースを割くべきかを再整理することが重要です。
データに基づく意思決定が成果を左右する時代へ
市場が大きく変動するタイミングでは、これまでの経験や感覚だけに頼った判断は大きなリスクにつながります。
特に病院システム分野では、
どのベンダーがどの領域に注力しているか、
電子カルテや医事会計といった注力キーワードの入札動向がどう変化しているか、
といった情報を定量的に捉え続けることが、戦略立案の前提条件になりつつあります。
継続的に追うべきデータは、例えば以下のようなものです。
| 企業別の落札・応札実績 | どの企業が、どの地域・どの分類の案件を落札しているかを時系列で把握する。 |
| キーワード別の応札傾向 | 「電子カルテ」「医事会計」など、領域別の案件動向や競合の動きを把握する。 |
これらのデータをもとにすることで、
「競合の動向把握」
「新規参入企業の早期察知」
「提案判断の優先度付け」
を客観的・戦略的に行うことが可能になります。
データを“戦略”に変える ― 入札BPOという選択肢
これらの取り組みの出発点となるのが、正確な情報収集と分析です。
しかし、全国の膨大な入札情報を網羅し、日々更新されるデータを手動で追跡するのは、多大な時間と労力がかかります。
そこで、ぜひご検討いただきたいのが、入札情報の収集・分析を専門家に任せる「入札BPO」という選択肢です。私たちは、入札情報サービス「NJSS」が日々収集している全国の入札案件データをもとに、貴社に特化した分析レポートを提供します。
- 競合企業別の落札・応札状況
- キーワード別(電子カルテ/医事会計等)の応札傾向
といった情報を、月次〜半期単位で定点的にご提供が可能です。
競合企業がどの領域に注力しているのか、新規プレイヤーがどこから参入してきているのかを早期に捉えることで、市場変化に先んじた戦略的な営業リソース配分が可能になります。
「正確な情報をもとに競合動向を把握したい」
「注力すべき領域やターゲットを明確にしたい」
「すぐに提案に活かせるデータがほしい」
このような課題をお持ちの企業様は、ぜひ一度、入札BPOをご検討ください。
入札情報の定点ウォッチから戦略への落とし込みまでを、ワンストップで支援いたします。


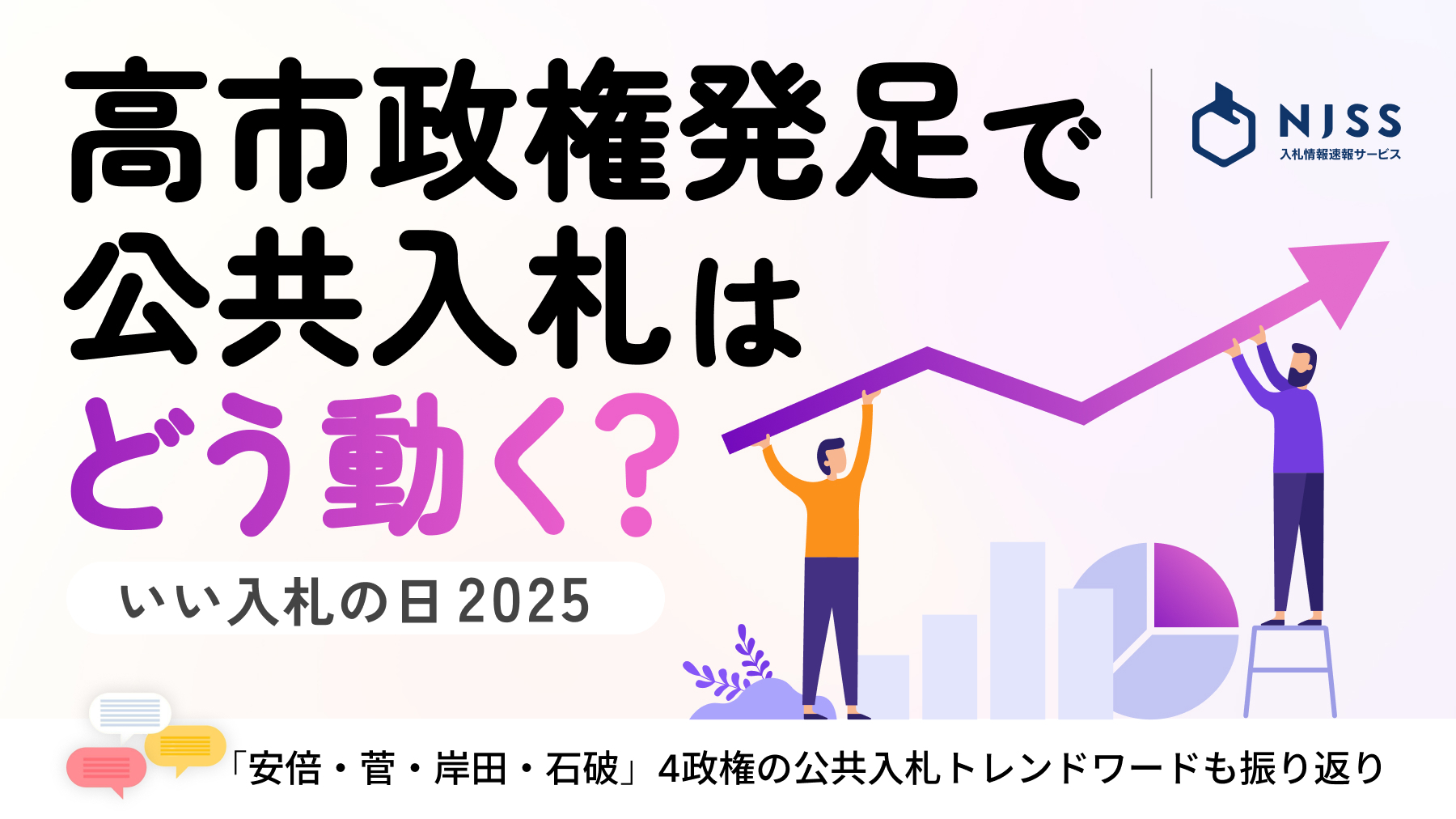
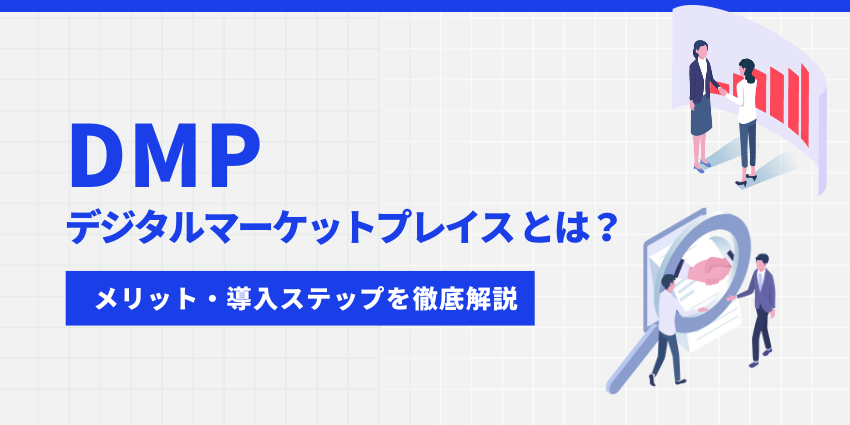




アイキャッチ.png)
.png)
.png)


