一般競争入札は、国や自治体が広く事業者を募集し、条件に合致すれば誰でも応募できる公平な入札制度です。過去の取引実績や人脈に依存せず、参加資格と価格を含む条件を満たす力があれば、中小企業にも十分なチャンスがあります。
本記事では、指名競争入札との違いや基本の流れ、落札率を高めるコツを解説します。一般競争入札にはじめて挑戦する方や、受注を増やしたいご担当者様はぜひ参考にしてください。
▶ 入札で新しい販路を開拓したい企業の方へ
のべ3,000社以上の相談実績と、NJSS運営16年以上の知見で
入札参入から落札ノウハウまで、入札アドバイザーがサポートします。
▶ 調達業務を効率化したい発注機関担当者の方へ
全国の自治体をはじめ9,000以上の官公庁が公示する調達情報の検索・閲覧が可能。
情報収集・仕様書作成・業者選定など日々の業務を大幅に効率化できます。
一般競争入札とは
一般競争入札は、国や自治体が発注する業務に対して、広く事業者から参加者を募る契約方式です。公告で参加条件を公開しており、資格を満たすすべての事業者が応募できる公平性の高い入札制度とされています。
会計法および地方自治法に基づき原則義務化されており、公共調達における透明性・競争性の確保を目的としています。主な特徴は、下記のとおりです。
- 実績や過去の取引に関係なく参加可能
- 価格競争を通じて公共財の効率的な調達が可能
- 地方自治体では指名競争入札からの移行も進行中
たとえば、建設業やIT業界では、中小企業が大企業と同じ条件で競争できる機会が拡大しています。とくに、総合評価落札方式の普及によって、価格だけでなく技術力・地域貢献・提案内容なども評価対象となり、競争の質も変化しています。
一般競争入札における落札方式の種類
一般競争入札では、入札に参加した事業者の中から、もっとも条件に適した企業を選ぶために落札方式が採用されています。代表的な落札方式は、下記の2つです。
- 最低価格落札方式:価格競争による従来型の落札方式
- 総合評価落札方式:価格と技術力を総合的に評価する方式
それぞれの特徴とポイントを見ていきましょう。
最低価格落札方式
最低価格落札方式は、予定価格の範囲内でもっとも低価格を提示した事業者が落札する方式です。手続きがシンプルでわかりやすいため、多くの中小企業が参入しています。
ただし、下記のような制限があります。
- 予定価格を1円でも超えると失格
- 最低制限価格を下回っても失格
たとえば、予定価格が1,000万円、最低制限価格が900万円の場合、900〜1,000万円の間で価格競争が行われます。精度の高い積算力が求められるため、過去の落札率や価格傾向を把握したうえで、戦略的に価格設定を行うことが重要です。
総合評価落札方式
総合評価落札方式は、価格だけでなく、技術提案や品質、安全性などの非価格要素を総合的に評価する入札方式です。
評価の方式は、下記のとおりです。
- 除算方式:評価値=技術点÷入札価格
- 加算方式:評価値=技術点+価格点
技術点は、標準点に加えて、下記のような加点項目から構成されます。
- 工事品質向上やICT活用提案
- 若手技術者の登用や女性技術者の配置
- ISO認証取得・BCP体制の整備
とくに中小企業にとっては、地域性や専門性を活かす加点提案が通用しやすく、大手企業と価格で張り合わずとも落札できる可能性があります。
一般競争入札とほかの入札方式との違い
一般競争入札のほかにも、契約方式には複数の種類があります。代表的なものは、下記の3種類です。
- 指名競争入札
- 企画競争入札(プロポーザル方式)
- 随意契約
ここでは、それぞれの特徴と一般競争入札との違いを解説します。
指名競争入札との違い
指名競争入札は、発注者があらかじめ選定した業者のみを指名し、その中で競争させる方式です。そのため、選ばれた企業以外は参加できず、選定基準が不透明になりやすいという課題があります。
これに対して、一般競争入札は公告によって広く参加者を募り、参加資格さえ満たせば誰でも応募できる開かれた制度です。両者の違いを、下表にまとめました。
| 項目 | 一般競争入札 | 指名競争入札 |
| 競争性 | 条件を満たせば誰でも参加可能 | 限られた指名業者間での競争 |
| 透明性 | 公告による情報公開で透明性が高い | 選定過程が不透明になりやすい |
| 参加対象 | 入札資格を満たす全企業が対象 | 発注者が選んだ企業のみ |
| 参加条件 | 公平な評価基準に基づく参加資格審査 | 過去の実績や関係性が重視されがち |
| 公告の有無 | 原則、公告により広く募集される | 一般的に非公開または限定的 |
参考
従来の指名競争では、地元の大手建設会社が指名されがちでしたが、一般競争入札では地域貢献実績のある中小企業にも機会があります。経営事項審査の点数や施工実績などの要件を満たせば、過去の指名実績に関係なく公平に参加可能です。
中小企業にとっては、自ら営業活動を行い、積極的に案件を取りに行ける土台となる方式といえるでしょう。
以下の記事では、指名競争入札について詳しく解説していますので、参考にしてください。
関連記事
一般競争入札と指名競争入札の違いとは?メリットやデメリットも解説
指名競争入札とは?一般競争入札との違いやメリットをわかりやすく解説
企画競争入札(プロポーザル方式)との違い
企画競争入札(プロポーザル方式)は、提案内容の独自性や技術力を重視する入札形式です。創造性が求められる業務や専門性の高い分野に適しており、選定は下記のような2段階で進められます。
- 第1段階:技術提案を評価し、優秀な事業者を選定
- 第2段階:選ばれた企業と価格交渉を実施(契約条件の調整)
一方で、一般競争入札(総合評価落札方式)は、価格と技術評価を同時に審査する1段階方式です。そのため、審査フローが簡素化されており、価格と提案のバランスを評価することが基本となります。
プロポーザル方式では、中小企業でも独創的な提案や地域密着型のアプローチで、高評価を得て大手企業に競り勝つ可能性があります。技術力に加え、提案力を発揮したい企業にとって、有利な入札方式です。
以下の記事では、公募型プロポーザル方式について詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
関連記事
公募型プロポーザル方式とは? 指名型・環境配慮型との違いやメリット・デメリットを解説
随意契約との違い
随意契約とは、発注者が競争を経ずに特定の事業者と直接契約を締結する方式のことを指します。少額契約や緊急対応、あるいは技術的に代替のない場合など、限定された条件下でのみ認められる例外的な契約手段です。
一方で、一般競争入札は、原則としてすべての契約に適用される公開型の調達方式です。すべての参加者に、公平な機会を提供しています。
主な違いと適用条件は、下表のとおりです。
| 項目 | 一般競争入札 | 随意契約 |
| 競争性 | 高い | なし(例外的) |
| 透明性 | 高い | 相対的に低い(近年は見直し傾向) |
| 主な適用条件 | 原則すべての契約 | 以下のいずれかに該当する場合のみ
・契約金額が少額 ・緊急時対応が必要 ・競争相手が存在しない(技術的独占など) |
| 少額契約の基準例 | 該当なし(原則すべて公告) | 【国・都道府県・政令市】
工事の請負:400万円以下 物件の借り入れ:150万円以下 【政令市を除く市区町村】 工事又は製造の請負:200万円以下 物件の借入れ:80万円以下 |
参考
随意契約は手続きが簡素でスピーディーに契約できる反面、法令で明確に例外要件が定められており、恒常的な受注手段にはなりません。中小企業としては、随意契約だけに依存せず、一般競争入札にも積極的に対応する体制づくりが安定的な受注につながります。
以下の記事で、随意契約について詳しく解説していますので、理解を深めたい方は参考にしてください。
随意契約とは?一般競争入札との違いや契約までのポイントを解説!
一般競争入札に参加するメリット
一般競争入札は、事業者と行政の双方にメリットが多い調達制度です。とくに新規参入や中小企業にとっては、ビジネスチャンスの拡大につながります。
ここでは、企業側と行政側の主なメリットを詳しく解説します。
| メリット | |
| 企業 | ・指名なしでも案件に参加できる
・公募情報が広く公開されている ・技術力や地域貢献を評価する総合評価落札方式が普及している ・災害協定や地域要件による加点制度がある |
| 行政 | ・評価基準が明示され、選定の透明性が高い
・公告・結果公表を通じて住民への説明責任を果たせる ・多様な提案によりコスト削減・品質向上が期待できる ・WTO協定にも準拠した国際基準の制度設計である |
企業側のメリット|新規参入でも公平に勝負できる仕組み
一般競争入札では、過去の取引実績や指名実績がなくても、参加資格を満たせば誰でも応募可能です。大手企業と同じ土俵で競争できるため、中小企業にとってはチャンスが広がります。
企業側が得られる主なメリットは、下記のとおりです。
- 指名なしでも案件に参加できる
- 公募情報が広く公開されている
- 技術力や地域貢献を評価する総合評価落札方式が普及している
- 災害協定や地域要件による加点制度がある
たとえば、若手技術者の育成体制や環境配慮の提案など、価格以外の要素で加点されるため、単純な価格競争に不利な企業でも受注が可能です。自社の技術や地域密着性を活かすことで、大手企業に勝る提案も実現できます。
行政側のメリット|透明性と公正性を担保できる調達制度
行政にとって、一般競争入札は公金を扱ううえでの説明責任・公平性・効率性を同時に満たす重要な制度です。行政側が得られる主なメリットは、下記のとおりです。
- 評価基準が明示され、選定の透明性が高い
- 公告・結果公表を通じて住民への説明責任を果たせる
- 多様な提案によりコスト削減・品質向上が期待できる
- WTO協定にも準拠した国際基準の制度設計である
従来は指名理由の説明が困難だったケースでも、一般競争入札なら公告・選定結果が公開されるため、住民や議会への説明責任を果たしやすくなります。
さらに、多くの応募者がいることで、想定外の技術提案やコスト見直し案が得られる可能性もあります。事前に複数事業者との関係性を築いておけば、災害時の緊急調達にも柔軟に対応できるでしょう。
一般競争入札に参加する際の注意点
一般競争入札は、公平で開かれた制度である一方、中小企業にとっては見落とせないリスクも伴います。主な注意点は、下記のとおりです。
- 激しい価格競争で利益確保が難しい
- 手続き・書類対応が煩雑で時間がかかる
- 要件の読み違いが不落の原因になる
- 落札できなければ準備のコストが無駄になる
詳しく見ていきましょう。
激しい価格競争で利益確保が難しい
最低価格落札方式では、価格が唯一の評価基準となるため、予定価格ギリギリの低価格で勝負する必要があります。無理な価格設定は、赤字や品質低下、納期遅延の原因にもなります。
具体的に注意すべきポイントは、下記のとおりです。
- 価格を下げすぎると利益が残らない
- 同額入札ではくじによる決定もある
- 無理なコスト削減で品質リスクが生じる
価格だけで競争するのではなく、総合評価落札方式で技術や提案力を武器にする戦略を立てることが、持続可能な受注につながるでしょう。
手続き・書類対応が煩雑で時間がかかる
一般競争入札は、事前の資格審査や提出書類が多く、発注機関ごとのルールに対応する柔軟性と工数が求められます。とくに中小企業では、人的リソースの圧迫が課題です。
中でも負担の大きい作業は、下記のとおりです。
- 参加資格・経営事項審査の取得
- 技術提案書・各種証明書の準備
- 電子入札システムの操作対応
中小企業では、これらの対応を限られたスタッフでこなさなければならないケースが多く、本来の業務に支障をきたすこともあります。こうした負担を軽減するには、専門家に書類作成を依頼する、テンプレート化を進めるなどの対策がおすすめです。
要件の読み違いが不落の原因になる
公告や仕様書の読み違いが原因で、参加資格を満たしていないと判断されるケースは少なくありません。形式不備や提出ミスも、即失格の対象になるため、注意が必要です。
注意が必要なのは、下記のようなミスです。
- 工事種別の読み違いによる実績要件の未達成
- 技術者の専任・非専任の誤解
- 技術提案書の文字数制限違反
- 電子入札の提出タイミングミス(1分遅れでも失格)
- 入札金額の入力ミス
入札締切が10時00分の場合、10時01分に提出してしまうだけで、即失格扱いになることがあります。
金額の入力ミスにも細心の注意が必要です。たとえば「1,200万円」と入力すべきところを、「12,000万円」と打ち間違えると、落札できても大幅な赤字を抱えるリスクがあります。反対に「120万円」と入力してしまうと、最低制限価格を下回り、失格となる可能性が高いです。
こうした失格リスクを回避するには、チェックリストによる事前確認や社内でのダブルチェック体制、不明点の積極的な発注者への照会が効果的です。とくに制度改正の直後は要件変更が起こりやすいため、最新情報を常に把握する体制も欠かせません。
落札できなければ準備のコストが無駄になる
多くの企業が応募する中で、落札できる確率は1~3割程度です。不調に終わると、かけた工数・費用がすべて無駄になるリスクがあります。
準備段階で発生しやすいコストは、下記のとおりです。
- 技術提案書の作成・調整工数
- 外部専門家の費用(積算・設計)
- 現地調査や関連機関との調整
- 他業務への影響(営業機会の損失)
このようなコストを最小限に抑えるには、やみくもに応募せず「勝てる案件に絞って挑む」戦略が不可欠です。過去の落札傾向や競合の参加状況を分析したうえで、事前に選別を行いましょう。
また、技術提案書のテンプレート化や、再利用可能な資料の蓄積を進めておくと、次回以降の準備時間とコストを大幅に削減できます。
一般競争入札の進め方・流れ
一般競争入札は、制度の仕組みを理解し、それぞれの工程で適切な準備を行えば、中小企業でも十分に受注のチャンスがあります。一般競争入札の進め方・流れは、下記のとおりです。
- STEP1:必要な入札参加資格を取得する
- STEP2:案件を探し、公告情報を確認する
- STEP3:仕様書・説明資料をもとに準備を進める
- STEP4:入札の実施と提出方法を選定する
- STEP5:契約を締結する
詳しく解説します。
STEP1:必要な入札参加資格を取得する
入札に参加するには、あらかじめ所定の参加資格を取得しておくことが絶対条件です。どれだけ高い技術力を持っていても、資格がなければ応募すらできません。
主な入札参加資格の種類は、下記のとおりです。
- 全省庁統一資格(物品・役務)
- 地方自治体ごとの独自資格
- 県単位での共同運営体
申請から取得までには通常1~3ヶ月を要するため、案件を探す前に資格取得を済ませておきましょう。とくに建設業は、決算後の経審申請を経て発注機関の入札参加資格が得られるため、スケジュール管理が重要です。
都道府県や市区町村などの地方自治体は、それぞれ独自の入札参加資格制度を設けています。申請手続きや要件は自治体ごとに異なりますので、対象の発注機関ごとに要件を確認しましょう。
STEP2:案件を探し、公告情報を確認する
資格を取得したら、次はどの案件に参加するかを選びます。案件情報は国や自治体の調達ポータルに掲載されており、公告内容をしっかり読み取ることが第一歩です。
公告で確認すべき主なポイントは、下記のとおりです。
- 参加資格の等級や地域要件
- 技術者の配置条件(資格や実績)
- 入札方式(価格重視か総合評価か)
- 提出期限・質問受付期間などのスケジュール
公告は読み落としが命取りになるため、複数人での確認やチェックリストの活用が有効です。また、過去の落札データや競合企業の動向を分析して、勝てる案件に絞って効率よく参入しましょう。
STEP3:仕様書・説明資料をもとに準備を進める
参加を決めた案件については、仕様書や設計図書をもとに積算や提案書作成を進めます。公告ではわからない品質基準や評価方法などの詳細な内容が、仕様書に記載されているため、読み解きが非常に重要です。
重要な準備作業は、下記のとおりです。
- 仕様書の読み込み:品質条件、工期、技術基準など
- 積算:材料費、人件費、標準歩掛の活用
- 技術提案書の作成:評価項目に沿った構成
- 必要書類の整備:証明書・履行実績など
提案書では、自社の強みを明確に示し、現地調査の結果なども踏まえた内容にすることで差別化を図れます。不明点がある場合は早めに照会し、精度の高い入札資料を整えましょう。
STEP4:入札の実施と提出方法を選定する
入札書の提出方法には電子・郵送・持参があり、発注機関ごとの指定にしたがって期限までに提出しなければなりません。とくに、電子入札は操作ミスや遅延による失格リスクが高いため、システム操作には慣れておく必要があります。
提出前に注意すべきポイントは、下記のとおりです。
- 電子入札なら電子証明書・ICカードが必要になる
- 入札書の署名・暗号化処理を正確に行う
- 提出は締切の30分前までに完了させる
- 入札方式によって提出内容が異なる
開札後は入札結果が公表されるため、他社の価格や評価内容を分析して次回の戦略に活かしましょう。
STEP5:契約を締結する
落札が決まったら、次は発注機関との正式な契約手続きに進みます。契約書や保証関連書類を整え、契約条件を十分に確認したうえで締結に臨みましょう。
契約時に求められる対応例は、下記のとおりです。
- 契約保証:契約金額の10%または履行保証保険
- 契約内容の確認:工期・変更手順・支払条件など
- 各種届出と書類提出:着手届・体制台帳・保険証など
契約後は、実施段階での変更契約や進捗報告、検査・請求対応といった履行管理が求められます。履行をきちんと行うことで、発注者からの信頼が高まり、次回以降の受注機会にもつなげられるでしょう。
一般競争入札の落札率を高める3つのコツ
一般競争入札の落札率を高めるためには、下記3つのコツを押さえておきましょう。
- 自社に合った案件を見極める
- 過去の落札価格・競合傾向をリサーチする
- 仕様書・要件を正確に読み解く
詳しく解説します。
自社に合った案件を見極める
入札での成功には、勝てる案件を選び抜く判断力が重要です。自社の得意分野や技術、資格などに合った案件を選ぶことで、無理のない提案ができ、落札率を高められます。とくに総合評価方式では、価格以外の強み(技術・地域貢献)での加点が結果に直結します。
案件選定時は、下記のポイントをチェックしましょう。
- 参加資格や等級を満たしているか
- 技術者の選任・資格条件をクリアしているか
- 同種業務・工事の実績があるか
- 地元業者としての加点(地元業者・災害協定など)があるか
効率よく案件を探したい方には、「NJSS(入札情報速報サービス)」の活用がおすすめです。キーワード・エリア・業種などを登録すると、条件に合致した入札案件を自動でメール通知してくれます。そのため、情報の見落としを防ぎつつ、効率的に案件を把握できます。
さらに、8,900以上の発注機関の情報を網羅しており、幅広い案件を一元的に収集できるのも魅力です。自社に合った案件だけに絞って、提案の精度を高めたい方は利用を検討してみてください。
過去の落札価格・競合傾向をリサーチする
過去データの分析は、勝てる価格帯や競合企業の動きを把握するうえで重要な工程です。
とくに最低価格落札方式では、過去の落札率を参考にすることで、適正な入札価格を設定しやすくなります。総合評価方式の場合は、評価項目や加点傾向の分析が、技術提案書の質を高める戦略づくりに役立つでしょう。
とくに分析すべきポイントは、下記のとおりです。
- 過去の落札率・予定価格との関係
- 常連企業・競合企業の応札傾向
- 評価項目と配点の変遷(総合評価方式)
- 地域・工種ごとの競争激化傾向
過去の落札価格を把握する際は、NJSSのサービスが便利です。全国の落札結果が網羅されており、条件検索・過去分析も簡単に行えます。
また、競合企業の応札傾向や地域別の入札頻度も可視化できるため、競合を避けて勝てる市場に絞るといった戦略も立てやすくなります。
どの案件にどの価格で挑めばよいか知りたい方は、NJSSの活用を検討してみてください。
仕様書・要件を正確に読み解く
失格リスクを減らし、落札率を上げるためには、仕様書と公告要件の正確な理解が必須です。一般競争入札では、参加資格や評価項目、提出書類が厳密に定められています。とくに総合評価方式では、加点要素を読み違えると落札が遠のくため、仕様書の理解は極めて重要です。
失格リスクを避けつつ、提案の質を高める具体的な対策は、下記のとおりです。
- 技術者要件・実績要件などの要件チェックリストの活用
- 評価項目の可視化と加点の事前整理
- 提出書類の三重チェック体制
- 電子入札における提出期限・文字数制限の厳守
- 曖昧な点は書面で照会・記録
なお、仕様書を読み込み、自社が参加可能な案件かどうかを見極めるのは大変な作業です。そのような場合におすすめなのが「入札BPO」です。仕様書の読み込みから適合可否の判断、必要書類の整理まで、専門チームが一括で代行してくれるため、人手不足の中小企業でも正確な入札対応が可能になります。
社内に専任担当者がいない企業でも、ミスなく正確に入札対応が進められる体制が整えられるでしょう。人的リソースに余裕がない中小企業にも、相性のよいサービスですので、利用を検討してみてください。
まとめ:制度の仕組みを理解して、入札で新たなチャンスを掴もう
一般競争入札は、公平なルールのもとであらゆる事業者にチャンスが開かれている制度です。過去の取引実績やコネに依存することなく、参加資格と適切な準備さえ整えば、大手企業と同じ土俵で勝負できます。
とくに、総合評価方式の普及によって、価格だけでなく、技術力や提案内容などの質でも勝機を掴めるでしょう。
とはいえ「仕様書の読み方がわからない」「落札に向けてどこを改善すればよいか不安」といったご担当者の方もいるでしょう。そのような方には、「入札アカデミー(運営:株式会社うるる)」の無料相談サービスがおすすめです。
入札情報サービス「NJSS」運営歴16年以上のノウハウで、企業の入札活動を全面サポートいたします。ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
▶ 入札で新しい販路を開拓したい企業の方へ
のべ3,000社以上の相談実績と、NJSS運営16年以上の知見で
入札参入から落札ノウハウまで、入札アドバイザーがサポートします。
▶ 調達業務を効率化したい発注機関担当者の方へ
全国の自治体をはじめ9,000以上の官公庁が公示する調達情報の検索・閲覧が可能。
情報収集・仕様書作成・業者選定など日々の業務を大幅に効率化できます。





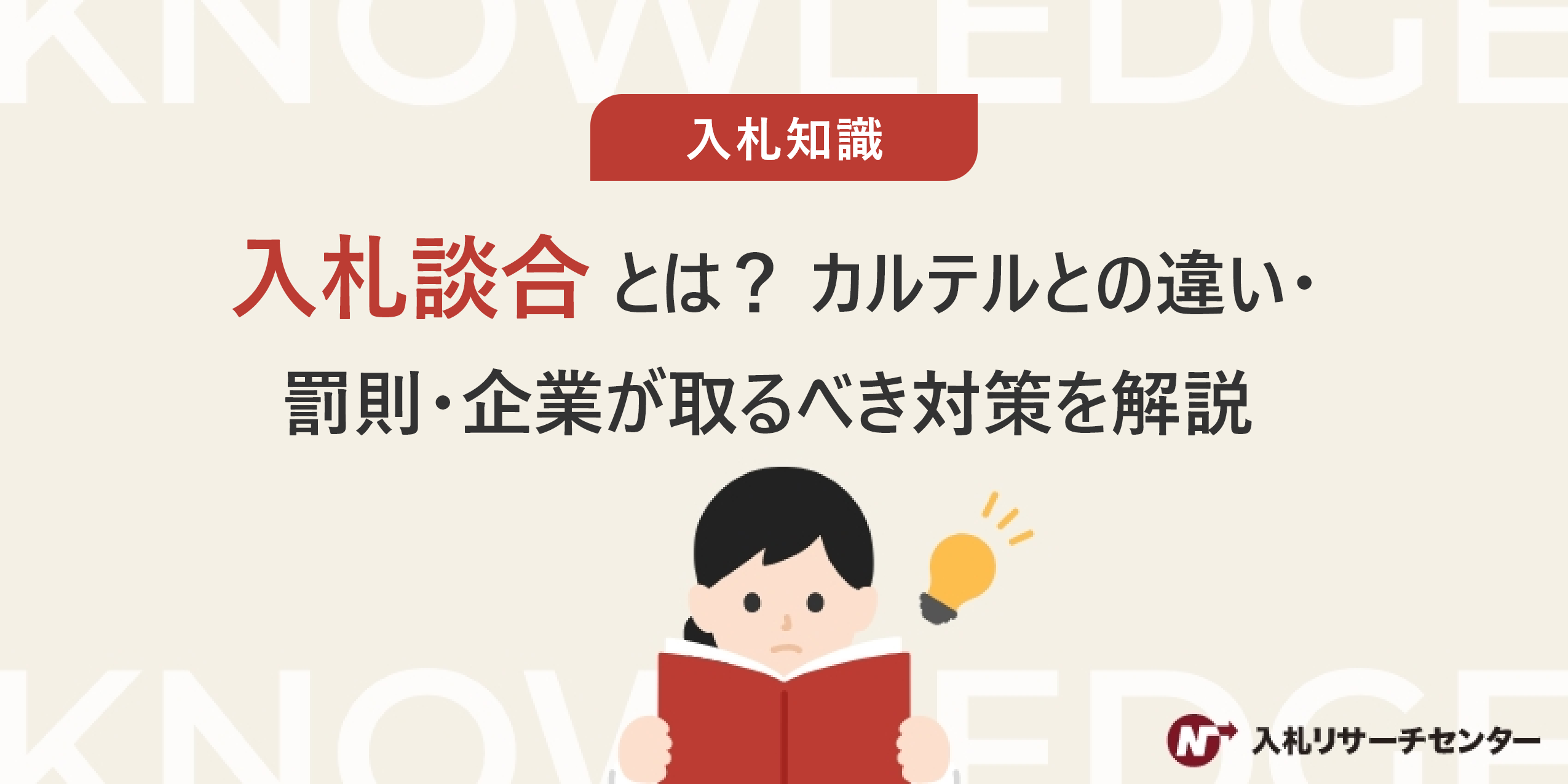

アイキャッチ.png)
.png)
.png)


