「入札」という名称からイメージできる通り、官公庁入札では、落札希望者のうちもっとも低価格を提示した者を採用する、入札方式が主流です。
しかし一部の案件では、価格だけでなく、企画提案内容全体を踏まえて落札事業者を決定するプロポーザル方式(企画競争入札)が用いられています。
本記事では、プロポーザル方式(企画競争入札)の概要と、落札のポイントについて、詳しく解説していきます。官公庁案件への新規参入や、価格以外の強みで勝負したい方は参考にしてみてください。
▶ 入札で新しい販路を開拓したい企業の方へ
のべ3,000社以上の相談実績と、NJSS運営16年以上の知見で
入札参入から落札ノウハウまで、入札アドバイザーがサポートします。
▶ 調達業務を効率化したい発注機関担当者の方へ
全国の自治体をはじめ9,000以上の官公庁が公示する調達情報の検索・閲覧が可能。
情報収集・仕様書作成・業者選定など日々の業務を大幅に効率化できます。
自治体のプロポーザル方式(企画競争入札)とは?
プロポーザル方式(企画競争入札)とは、不特定多数の企業の中から定められたテーマの企画書・提案書などの提出を求め、もっとも適した提案をした企業を契約の相手とする方式です。自社の提案力・企画力を適切にアピールできれば、入札額に左右されずに落札される可能性があります。
近年、官公庁入札においては、応札金額によって落札者を決定する「一般競争入札」の割合が増加しています。一方で、中小企業の中には、価格競争力よりも、提案力・企画力に強みをもつ企業が少なくありません。
こうした実情を踏まえ、下記のような業務ではプロポーザル方式が採用されるケースが多く見受けられます。
- 建築コンサルタント業務(公共工事・建築物設計・調査など)
- システムにかかるコンサルティング業務
- 語学研修業務
- PFI(民間資金活用)事業に関するアドバイザリー業務
中小企業にとっては、価格競争ではなく提案力で勝負できるチャンスのある入札形式として注目されています。
プロポーザル方式と入札の違い
一般競争入札は、広く事業者に参加を募り、もっとも条件のよい入札者を選定する方式です。主に「最低価格落札方式」が採用されるため、適正な価格で契約を結べる利点があります。しかし、参加事業者が多い分、価格競争が激化し、利益率が低下する可能性もあります。
一方、プロポーザル方式は、価格だけでなく下記のような点が審査対象です。
- 提案内容の具体性や実現可能性
- 技術力や専門性
- 独自のアイデアや工夫
- 発注者の課題に対する解決力
「何ができるか」「どう解決するか」といった質的な部分が重視される方式です。業務の特性や、課題に応じた柔軟な提案が求められる業務に適した方式といえます。
プロポーザル方式の種類
プロポーザル方式(企画競争入札)には、案件の性質や目的に応じて3つの主要な形式があります。いずれも価格だけでなく、提案内容や実績などを総合的に評価し、事業者を選定する点が共通しています。主な種類は、下記のとおりです。
- 公募型プロポーザル方式
- 指名型プロポーザル方式
- 環境配慮型プロポーザル方式
それぞれの特徴を見ていきましょう。
公募型プロポーザル方式
公募型プロポーザル方式は、もっとも広く利用されている標準的な形式です。すべての参加条件を満たす事業者に対し、平等に提案の機会が開かれます。
市民向け事業や広報関連業務などで活用され、はじめての参入にも適した方式です。メリット・デメリットは下記のとおりです。
| メリット | デメリット |
|
|
新規参入のきっかけに有効な方式であり、自治体にとっても説明責任を果たしやすく、初導入にも適しています。
指名型プロポーザル方式
指名型プロポーザル方式は、発注者である自治体があらかじめ選定した企業のみに提案を依頼する方式です。専門性や信頼性が求められる案件に多く用いられます。
システム更新や政策立案支援などで広く採用されています。メリット・デメリットは、下記のとおりです。
| メリット | デメリット |
|
|
受注機会を得るには、中長期的なブランディングや情報発信、自治体との信頼関係づくりが不可欠です。
環境配慮型プロポーザル方式
環境配慮型プロポーザル方式は、2007年の「環境配慮契約法」に基づき、国や自治体、独立行政法人などが導入を進めている形式です。提案内容における環境負荷の低減や持続可能性の観点が重視され、大規模なインフラ整備・公共施設事業などで用いられています。
メリット・デメリットは、下記のとおりです。
| メリット | デメリット |
|
|
環境方針に即した提案を行うには、事前の準備や体制構築が求められます。自治体の環境戦略と整合性の取れた提案が成功のポイントです。
プロポーザル方式と他の入札方式との違いを比較
業務内容や目的に応じて、地方自治体ではさまざまな入札方式が採用されます。プロポーザル方式は、価格だけではなく、提案の質や課題解決力を重視する点で、他の方式とは大きく異なります。
ここでは、比較対象として「総合評価落札方式」と「自治体向けコンペ」の2つを取り上げ、それぞれとの違いを見ていきましょう。
総合評価入札とプロポーザル方式の違い
総合評価落札方式とプロポーザル方式は、どちらも価格だけでなく、内容や質を重視して契約相手を選定する方式です。しかし、評価基準や適用分野に違いがあります。
総合評価落札方式は、価格に加え技術力や実績、品質などを総合的に評価して事業者を選定する方式です。価格のウェイト(比重)が高めに設定される場合が多く、コストパフォーマンスを重視した業務に適しています。主に公共工事や定型的な業務で活用されており、評価基準が数値化されるため、公平性と透明性が確保されやすい点も特徴です。
一方、プロポーザル方式は事業者が提案書を提出し、提案の質や独自性、課題解決能力などを重視して選定される方式です。高度な専門性や創造性が求められる案件に適しており、調査研究や政策立案、ITシステム構築などで活用されます。
総合評価落札方式が効率性を重視する一方、プロポーザル方式は最適な提案を求める点が大きな違いです。
自治体向けコンペとプロポーザル方式の違い
コンペとプロポーザルは、いずれも事業者から提案を募る点で共通しています。しかし、コンペは主にデザインやアイデアを競う場であり、最優秀案を選定することが目的です。提案内容が採用されても、契約につながらないケースもあります。
一方、プロポーザル方式は具体的な業務遂行の提案を求め、提案内容にもとづいて契約相手を選定します。実施体制や実績、課題解決のアプローチなど、実務的な要素が重視されるのが特徴です。
コンペはアイデアの競争、プロポーザル方式は業務提案の競争であり、目的と成果物の扱いが異なる点に注意が必要です。
プロポーザル方式のメリット
プロポーザル方式のメリットは、下記のとおりです。
- 見積もり価格を過度に下げずに済む
- 独自の強みをアピールできる
- 実績や技術力が正当に評価される
- 自治体との協業・信頼構築のチャンスにつながる
詳しく解説します。
見積もり価格を過度に下げずに済む
「一般競争入札」の場合、他の落札希望者よりも低価格を狙うことで、予算ギリギリの案件を獲得してしまうケースも少なくありません。このような場合、受注数が増えたとしても利益にはつながりにくいでしょう。
一方、プロポーザル方式(企画競争入札)では提案する企画の内容が評価対象となるため、価格を不当に下げる必要がありません。結果として、適正な予算での提案が可能になり、利益を確保しやすくなります。
独自の強みをアピールできる
プロポーザル方式では、提案書やプレゼンテーションを通じて、自社の独自性や専門性を前面に出すことが可能です。とくに、下記のような要素が評価される傾向にあります。
- 他社にない企画力や地域特化のアイデア
- SNS活用など独自の広報戦略
- 成果につながった過去の成功事例
このように、価格以外の付加価値で評価されるため、強みを活かした提案がしやすいのが特徴です。
実績や技術力が正当に評価される
プロポーザル方式では、事業者のこれまでの実績や担当者の専門性など、定量的な評価だけでは測れない能力も加味されます。たとえば、下記のような点が評価対象になります。
- 同種・類似業務の受託実績
- 担当者の資格や経験年数
- セキュリティやアクセシビリティ対応の技術
これにより、過去の信頼ある業務経験や技術的知見が正当に評価されやすくなり、実力に見合った案件獲得のチャンスが広がります。
自治体との協業・信頼構築のチャンスにつながる
プロポーザル方式では、選定後に自治体と協議を行い、提案内容を具体化・最適化していく機会が設けられています。その過程で、次のような効果が期待できます。
- 契約前の協議で課題や方針をすり合わせ
- 業務の目的達成に向けて共同で戦略を立案
- 継続的なパートナーシップにつながる実績形成
このように、単発の受託にとどまらず、自治体との中長期的な関係性を築くきっかけにもなるでしょう。
プロポーザル方式のデメリット
前述の通り、「企画競争入札(プロポーザル方式)」はコンペ形式で行われることから、提案書の作成やプレゼンテーションの用意など、入札前の準備にかかる負担が「一般競争入札」などと比較して大きいことがデメリットとして挙げられます。
プロポーザル方式には多くの利点がありますが、事業者側にとっての負担や公平性の課題もあります。ここでは、実務上指摘されやすい3つのデメリットについて解説します。
- 提案書作成に時間とリソースがかかる
- 過去の実績や一定の経験値が求められることがある
- 選定基準の透明性に疑問が生じることがある
詳しく見ていきましょう。
提案書作成に時間とリソースがかかる
プロポーザル方式は、提出書類の内容が評価の中心となるため、入札前の準備に多くの時間と労力が必要になります。
- 提案書の作成・資料収集・文書化
- プレゼンテーション資料の準備やリハーサル
- 社内調整や外注先との連携対応
このように入札前の準備にかかる負担が「一般競争入札」と比較して大きいことが、デメリットとして挙げられます。
過去の実績や一定の経験値が求められることがある
プロポーザル方式では、過去の実績が重要な評価項目とされます。そのため、実績の少ない事業者には参入障壁が生じやすい構造があります。
よくある要件の例は、下記のとおりです。
- 過去5年以内に同規模自治体での導入実績が3件以上
- 同種業務に関する受託実績の明記
- 担当予定者の資格や経験年数の提示
これにより、技術力や提案力があっても、実績が少ない新興企業や中小企業が評価されにくくなるという課題が指摘されています。今後は、評価軸の見直しや共同体参加の促進も必要です。
選定基準の透明性に疑問が生じることがある
プロポーザル方式は、定量化が難しい項目を評価するため、選定過程に主観が入る余地があり、透明性への懸念が生じやすくなります。主な問題点は、下記のとおりです。
- 評価基準や配点の曖昧さ
- 選定委員と参加事業者の接触リスク
- 評価プロセスの非公開・不十分な説明
このような点から、住民や他の事業者からは「出来レース」などと批判されるケースもあります。信頼性を高めるには、評価基準・選定理由の公表や、第三者の選定委員の参加が不可欠です。
公募型プロポーザルの流れ
公募型プロポーザル方式では、入札参加から審査結果の通知までに複数のステップがあります。各段階で必要な対応を正しく理解しておくことが、円滑な入札活動と落札の可能性を高める第一歩です。
公募型プロポーザルの基本的な流れは、下記のとおりです。自社の準備状況と照らし合わせながら、抜け漏れのないようチェックしてみてください。
| ステップ | 内容 |
| 1.案件を探す | 公告を確認し、業務内容や参加条件を把握する |
| 2.説明会に参加する | 発注者の意図や詳細を理解するために出席する |
| 3.参加申請をする | 指定書類をそろえて、期限内に提出する |
| 4.不明点を質問する | 公告や仕様書の不明点を事前に確認・質問する |
| 5.提案書を提出する | 課題解決策や自社の強みを整理して提出する |
| 6.プレゼンテーションを行う | 必要に応じて、提案内容を口頭で説明する |
| 7.審査結果を確認する | 結果通知を受け取り、採択時は契約へ進む |
このように全体の流れを把握しておくことで、各段階における目的や準備内容が明確になります。とくにはじめての入札では、事前にスケジュールを整理し、余裕を持って準備を進めましょう。
自治体のプロポーザル案件を探す3つの方法
プロポーザル方式での案件獲得を目指すためには、提案余地のある案件を探したうえで、提案に臨む必要があります。自治体のプロポーザル案件を探す方法は、以下の3つです。
- 自治体の公式サイトで直接確認する
- 入札情報サービスを活用する
- 自治体の予算・計画書から兆しを探る
1.自治体の公式サイトで直接確認する
プロポーザル案件は、基本的に各自治体の公式サイトにて公示されます。もっとも確実で、詳細な情報が得られる手段です。
おもな掲載場所は、下記のとおりです。
- 「入札・契約情報」ページ
- 「調達情報」ページ
- 政策企画課、情報政策課、広報課などの部署ページ
- 年間発注予定表(調達スケジュール)
自治体によって掲載場所が異なるため、対象自治体の構成を把握したうえで定期的に確認することが重要です。RSS配信やメールマガジンがある場合は、登録しておくと情報を見逃しにくくなります。
2.入札情報サービスを活用する
プロポーザル方式は事前準備に時間がかかるため、案件を早期に把握することが落札の成否を大きく左右します。そこで活用したいのが、入札情報サービスです。複数の自治体案件を一括で検索・比較でき、効率的にチャンスを広げられます。
代表的な入札情報サービスは、下記のとおりです。
- 各都道府県の電子調達システム
- 調達ポータル
- 入札情報速報サービス「NJSS」
入札情報サービスの中でも、株式会社うるるが提供する「NJSS」は、全国8,900以上の発注機関の入札案件を網羅しています。プロポーザル案件も多数掲載されており、自社の得意分野に合った案件を効率よく見つけられるでしょう。
また、「発注機関」や「キーワード」、「入札日」などの絞り込み検索が可能なため、自社に合った案件探しをスムーズに行える点も魅力です。事前準備に時間をかけたい方や、これから自治体案件への参入を強化したい企業に適しています。
NJSSは無料でお試しできるので、入札業務の効率化に課題を感じている方は、ぜひNJSSの導入を検討してみてください。
3.自治体の予算・計画書から兆しを探る
プロポーザル案件は、予算化されてから実際に公示されるまで数ヶ月~1年のタイムラグがあります。そのため、自治体の年度予算や行政計画を事前にチェックすることで、今後公募されそうな事業の兆しをつかめます。
とくに総合計画や中長期計画には、今後の重点施策・予算配分の方向性が記されており、提案活動のヒントになるでしょう。ただし、こうした情報は自治体ごとに分散しているため、自社で網羅的に調査するのは手間がかかります。
そこで活用したいのが、株式会社うるるの「GoSTEP」です。GoSTEPは、全国の自治体や省庁の予算・行政資料を一括検索できるツールです。注力分野や地域に絞り、効率よく情報を収集できます。
GoSTEPは無料でトライアル可能ですので、入札前段階の上流情報の収集や活用に課題を感じている方は、ぜひ一度体験してみてください。
「プロポーザル方式(企画競争入札)」落札のための5つのポイント
「一般競争入札」は価格だけで勝敗が決まるため、官公庁入札がはじめての方でも、取り組みやすい形式です。一方で、プロポーザル方式(企画競争入札)の場合、案件を落札するためには知っておきたいポイントが複数あります。重要なポイントは下記の5つです。
- 官公庁・自治体の組織体制について理解しておく
- 官公庁・自治体の予算成立スケジュールを把握しておく
- 発注機関の意図を汲み取った提案書を作成する
- 提案の訴求点を絞り込む
- 他社との差別化ポイントを明確にする
詳しく解説します。
1.官公庁・自治体の組織体制について理解しておく
公示された案件について、企業が適切な提案をするためには、案件を公示している部署の役割や課題を把握しておくことが前提です。たとえば同じ「観光推進」でも、観光課・地域振興課など所管部署によって重視する視点が異なる場合があります。
発注機関の組織図や近年の施策を事前に調べておくことで、的を射た提案につながります。
2.官公庁・自治体の予算成立スケジュールを把握しておく
官公庁入札においては、同様の案件が定期的に公示されているケースがあります。
「プロポーザル方式(企画競争入札)」は、「一般競争入札」などと比較して、入札のための準備に時間を要します。案件が発生しそうなタイミングを予測し、事前準備をスムーズに進めておくと競争相手に優位性を築けるでしょう。
その際に役立つのが「予算成立スケジュール」です。自治体では予算が成立したあと、数ヶ月~1年後に案件が公示されるケースも多いため、予算案の段階から動向を追っておくと、他社より早く準備を進められます。
3.発注機関の意図を汲み取った提案書を作成する
プロポーザル方式では、価格だけでなく提案の内容や妥当性が評価されます。有効な企画・提案を行うためには、発注機関の意図を汲み取っておくことが重要です。
多くの案件では通常、公募説明会(※)で発注機関の意図が解説されるため、必ず参加し、不明点は質問を投げかけるようにしましょう。意図とズレのない企画書を作成することが、評価アップにつながります。
(※)官公庁入札において、発注機関側が案件の内容について詳細を説明する場。説明後に質疑応答の時間が設けられるケースが多い。
4.提案の訴求点を絞り込む
プロポーザル方式では、さまざまな強みをもつ事業者が入札に参加するため、提案内容が埋もれてしまうリスクがあります。
自社の強みや特徴をすべて盛り込むのではなく、提案を明確にして訴求点を絞り込むことが重要です。提案の核となるポイントをひとつに定め、それを軸に説得力ある構成を意識しましょう。
「業界特化の実績」や「地域密着の支援体制」など、自社ならではの強みを具体的に示すことで、印象に残る提案が可能です。
5.他社との差別化ポイントを明確にする
プロポーザル方式では、他社との比較で優位性を示すことが求められます。自社の強みだけでなく、「他社にはない独自性」や「他社より優れている点」を明確にすることが重要です。
たとえば、下記のような観点で差別化を図れます。
- 地域密着型の支援体制(大手にないきめ細かさ)
- 施策後のフォロー体制(導入後支援の充実)
- 過去の成功事例の自治体類似性(ニーズの的中率)
また、公募説明会では他社の参加状況や特徴も観察し、競合分析を踏まえて訴求内容を調整すると効果的です。選定者に「選ぶ理由」を与えましょう。
まとめ| プロポーザル方式を理解し、効果的な提案書作成につなげよう
プロポーザル方式(企画競争入札)で落札するには、事前準備こそが落札の成否を分けます。スムーズな事前準備のためには、時間的な余裕を作るための、入札関連業務の効率化が不可欠です。
限られた時間の中でこうした情報を収集・整理するには、専門的なサポートを活用するのが効果的です。「入札アカデミー」では、入札未経験の企業や、落札率を高めたい方に向けた無料の入札相談を実施しています。
「何からはじめるべきかわからない」「うちも入札に参加できるの?」という段階からでも相談可能です。3,000社以上の支援実績をもとに、プロのアドバイザーがマンツーマンで丁寧にサポートいたします。入札に関するお悩みがある方は、気軽にご活用ください。
▶ 入札で新しい販路を開拓したい企業の方へ
のべ3,000社以上の相談実績と、NJSS運営16年以上の知見で
入札参入から落札ノウハウまで、入札アドバイザーがサポートします。
▶ 調達業務を効率化したい発注機関担当者の方へ
全国の自治体をはじめ9,000以上の官公庁が公示する調達情報の検索・閲覧が可能。
情報収集・仕様書作成・業者選定など日々の業務を大幅に効率化できます。








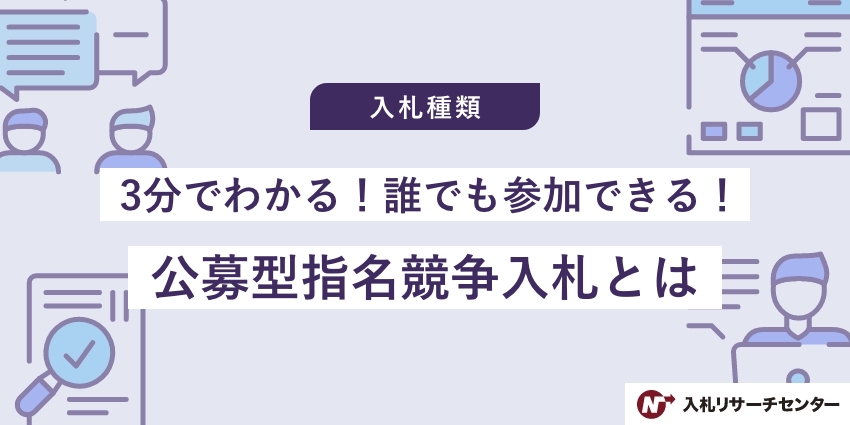
アイキャッチ.png)
.png)
.png)


