落札を勝ち取るためには「最低制限価格制度」の理解と、戦略的な価格設定が不可欠です。
多くの発注機関が採用するこの制度は、落札者を決める重要な要素であり、制度を理解しなければ最適な価格設定はできません。
入札担当者には、最低価格の基準を踏まえたうえで、自社の利益を確保しながらも、競合他社の一歩先を行く価格設定が求められるでしょう。しかし、最低価格の基準を満たした数値を算出するのは容易ではありません。
そこで本記事では、希望金額での落札を勝ち取るための役立つ知識を紹介します。
落札率向上を目指すご担当者様は、ぜひ参考にしてください。
▶ 入札で新しい販路を開拓したい企業の方へ
のべ3,000社以上の相談実績と、NJSS運営16年以上の知見で
入札参入から落札ノウハウまで、入札アドバイザーがサポートします。
▶ 調達業務を効率化したい発注機関担当者の方へ
全国の自治体をはじめ9,000以上の官公庁が公示する調達情報の検索・閲覧が可能。
情報収集・仕様書作成・業者選定など日々の業務を大幅に効率化できます。
最低価格落札方式の基礎と制度
工事やプロジェクトの入札において「最低価格落札方式」は最も一般的な落札方式です。入札価格のみで落札者を決定するため、透明性が高く、競争原理が働きやすいという特徴があります。
ここでは、以下3つの制度について解説します。
- 最低制限価格制度
- 低入札価格調査制度
- 変動型最低制限価格制度
落札率を上げるためには、制度概要への深い理解が欠かせません。
最低制限価格制度
「最低制限価格制度」とは、入札価格があらかじめ設定された一定の金額を下回った場合、その入札を無効とする制度です。公共工事をはじめ、多くの入札で最低制限価格が設定されています。
「最低価格」は、入札された価格のなかで最も低い価格を指します。一方「最低制限価格」は、それ以下の価格での入札を認めないラインです。
たとえば最低制限価格が1,500万円に設定されていた場合、1,490万円で入札した企業は失格となります。最低価格と最低制限価格の違いを理解することは、入札戦略において非常に重要です。
低入札価格調査制度
「低入札価格調査制度」とは、入札価格が著しく低い場合に、発注機関が受注者に対しその価格で契約を履行できるか調査する制度のことです。
調査の結果、発注が困難と判断された場合、その落札は無効となります。これは、ダンピング受注による工事などの品質低下防止や、契約の確実な履行確保が目的です。
なお、落札が無効となった場合、2番目に低い価格を提示した事業者が落札者となります。
参照:総務省「低入札価格調査制度・最低制限価格制度について(詳細)」
変動型最低制限価格制度
「変動型最低制限価格制度」とは、入札後の応札価格をもとに、一定の計算式で「最低制限価格」を算出する方式のことで、従来の方式よりダンピング抑止効果が高いとされています。
計算式は地方自治体ごとに異なり、開示・非開示いずれの場合もあるため、入札公告や仕様書での事前確認が必須です。
最低制限価格を下回る入札者は失格となり、上回るなかで最も低い価格の入札者が落札者となる点は、従来の制度と同様です。
最低制限価格制度が必要な理由
工事やプロジェクトの入札において、最低制限価格制度が必要な理由は、主に以下の3点です。
- ダンピング防止と品質確保
- 公正な競争環境の維持
- 入札参加者の利益保護
過度な価格競争は受注者の利益を圧迫し、品質低下や契約不履行のリスクを高めます。最低制限価格を設定することで、適正な利益を確保したうえで工事やプロジェクトに臨めるでしょう。
また最低制限価格を設定することで、資金力のある企業によるダンピング競争を抑制し、中小企業にも公平な競争機会を与えられるようになります。
そして、最低制限価格を設定することは入札参加者の利益保護の観点でも重要です。最低制限価格を設けない場合、極端に安い価格で落札される可能性があり、利益を確保できないケースが考えられます。
無理のない入札価格で勝負できれば、企業は安定的な経営が行えるようになるでしょう。
最低制限価格制度の価格の決め方は?
ここでは最低制限価格の決め方について、代表的な2つの方法を解説します。
- 予定価格に一定の割合を乗じて算出する方法
- 必要経費を積み上げて算出する方法
なお、最低制限価格の決め方は、全国一律ではありません。指針として「中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル」の資料が公開されており、多くの地方自治体で参考にされています。
参照:国土交通省/ダンピング対策の更なる徹底に向けた低入札価格調査基準及び最低制限価格の見直し等について
予定価格に一定の割合を乗じて算出する方法
「予定価格 × 〇〇%」のように、予定価格に一定の割合(掛率)を乗じて、最低制限価格を計算する方法です。最もシンプルな算出方法であり、多くの地方自治体で採用されている方法です。
具体例として、神奈川県のホームページでは以下の記載があります。
【最低制限価格率】
・一般業務委託:83%
・印刷物の請負:70%
参照:神奈川県ホームページ/入札における最低制限価格制度の適用について
このように、請け負う内容によって最低制限価格の割合が変わるケースもあります。
計算が容易でわかりやすいメリットがある一方で、経費や資材価格が細かく考慮されず、正確な利益を算出しづらい点がデメリットです。
必要経費を積み上げて算出する方法
割合だけで最低制限価格を決められない案件では、経費を細かく洗い出して算出することもあります。
一例として、経費の区分には以下のようなものがあります。
- 直接工事費
- 共通仮設費
- 現場管理費
- 一般管理費
これらの経費を以下のような計算式に当てはめて、最低制限価格を設定します。
「直接工事費 × 90% + 共通仮設費 × 80% + 現場管理費 × 80% + 一般管理費 × 50%」
必要な経費をより正確に反映できるメリットがある一方、計算の工数がかかる点がデメリットです。
必要経費は案件によって異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。
最低制限価格制度を踏まえた入札の戦略4選
ここまで、最低制限価格について解説しましたが、これらを踏まえて落札の機会を増やすための4つのポイントを解説します。
- 情報収集で最低制限価格を予測する
- 競合他社の分析で入札価格の傾向を探る
- 自社のコスト構造を把握したうえで適切な価格を算出する
- 競争倍率の低い案件に臨む
入札案件を成功に導くための対策については、以下の記事でも詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。
関連記事:【自治体向け営業】入札案件攻略のための3つの必須対策!
情報収集で最低制限価格を予測する
落札を勝ち取るためには、過去の落札結果や最低制限価格、予定価格などのデータを入手し分析することが大切です。
最低制限価格の予測の精度を高めるためには、案件種別や発注機関ごとにデータを分析して、傾向を把握することがポイントとなります。
なお、詳細な情報収集には人的コストがかかるため、情報収集サービスの利用をおすすめします。
国内の入札情報を効率的にチェックしたい方は、全国8,800以上の発注機関の案件を一括検索できる入札情報速報サービスNJSSをぜひご利用ください。
関連サイト:入札情報速報サービスNJSS
競合他社の分析で入札価格の傾向を探る
入札戦略のひとつとして、競合他社が過去にどのような価格で入札しているか、またその結果(落札・失注)を調査することも重要です。
競合他社の情報を把握することで、競合の強みや弱みを理解し、自社の強みを活かした差別化戦略が行えるようになります。競合の動向を把握することは、より有利な価格設定につながります。
自社のコスト構造を把握したうえで適切な価格を算出する
利益を確保しながら競合他社よりも有利な価格設定をするためには、すべての必要経費を積算し、必要なコストを正確に割り出すことが肝心です。
過去の実績や業界平均などを参考に、コストと利益を考慮したうえで、競争力のある入札価格を決定しましょう。
適切な価格設定は、落札の可能性を高めるだけでなく、自社の利益を確保するうえでも重要です。
競争倍率の低い案件に臨む
注目度の高い入札案件は競合企業が多く、価格競争が激化しやすい傾向にあります。かろうじて落札できたとしても、十分な利益を確保できなければ受注するメリットがありません。
入札経験が少ない企業の場合、激しい価格競争を避けるために、比較的注目度の低い案件に挑戦することを推奨します。競合が少なければ適切な価格での入札が可能となるため、利益を多く残せる可能性が高いでしょう。
入札における最低制限価格制度に関するよくある質問
最後に、入札における最低制限価格制度に関する以下の質問に回答します。
- 最低制限価格制度が設定されない理由は?
- 最低制限価格を公表しない理由は?
入札の制度や仕組みに加え、発注機関の意図を理解することで、逆算的な戦略を立てやすくなるでしょう。
最低制限価格制度が設定されない理由は?
発注機関が最低制限価格制度を設定しない理由はさまざまですが、主に以下の要因が考えられます。
- 競い合わせて最も低価格で発注したい
- ダンピングリスクが低い
- 価格以外の要素を重視したい
発注機関が入札参加者間で自由に価格競争させたい場合、最低制限価格を設定しないことがあります。あらかじめ目安額が分かっていると、競い合いが起きにくくなるためです。
また案件の性質上、ダンピングリスクが低いと判断される場合は、最低制限価格を設定しないケースが考えられます。たとえば、専門性が高く価格競争になりにくい案件などが該当します。
価格だけでなく、技術力や実績など、他の要素を総合的に評価して落札者を決定したい場合、最低制限価格を設定しないことがあります。
どのような理由であるかは公表されないため、経験にもとづいて予想するほかありません。
最低制限価格を公表しない理由は?
発注機関が最低制限価格を公表しない理由は、主に以下の点が挙げられます。
- 可能な限りの最低価格で入札させたい
- ダンピングを助長する可能性があるため
- 特定の入札者が有利になる可能性がある
最低制限価格を事前に公表することは、一見すると透明性を高めるように思えますが、常に最良の結果につながるとは限りません。場合によっては、その公表が競争を阻害し、不利益を生じさせるおそれがあります。
具体的には、最低制限価格を開示すると、入札価格がその価格付近に集中することが考えられます。これは、本来であればより低い価格での入札が可能でも、入札者が無難な選択をしやすいために起こる現象です。
さらに最低制限価格の公表は、ダンピング競争を誘発するリスクも否定できません。入札参加者は、公表された価格を下回らない範囲で、極力低い価格を提示しようとします。その結果、落札者が十分な利益を確保できない場合があるでしょう。
加えて、最低制限価格を公表することで、一部の入札者がその情報を不正に入手することも懸念されます。これらの要因は公正な競争を妨げ、発注機関側への不利益をもたらすことにもつながりかねません。
こうした理由から、最低制限価格の公表をあえて回避することがあります。
最低制限価格制度を理解したうえで勝ち筋を見つけよう
本記事では、最低制限価格制度の基礎知識から、発注機関ごとの算出方法の違いなどを解説しました。最低制限価格を意識した実践的な入札戦略として、情報収集の重要性や競合分析について、担当者はよく理解しておくべきでしょう。
競争力のある価格設定を行うことが落札への近道となりますが、ベストな数値を設定するのは非常に難しいものです。より高度な分析と戦略を立てるためには、専門的なサポートサービスの活用を視野に入れることが得策です。
▶ 入札で新しい販路を開拓したい企業の方へ
のべ3,000社以上の相談実績と、NJSS運営16年以上の知見で
入札参入から落札ノウハウまで、入札アドバイザーがサポートします。
▶ 調達業務を効率化したい発注機関担当者の方へ
全国の自治体をはじめ9,000以上の官公庁が公示する調達情報の検索・閲覧が可能。
情報収集・仕様書作成・業者選定など日々の業務を大幅に効率化できます。
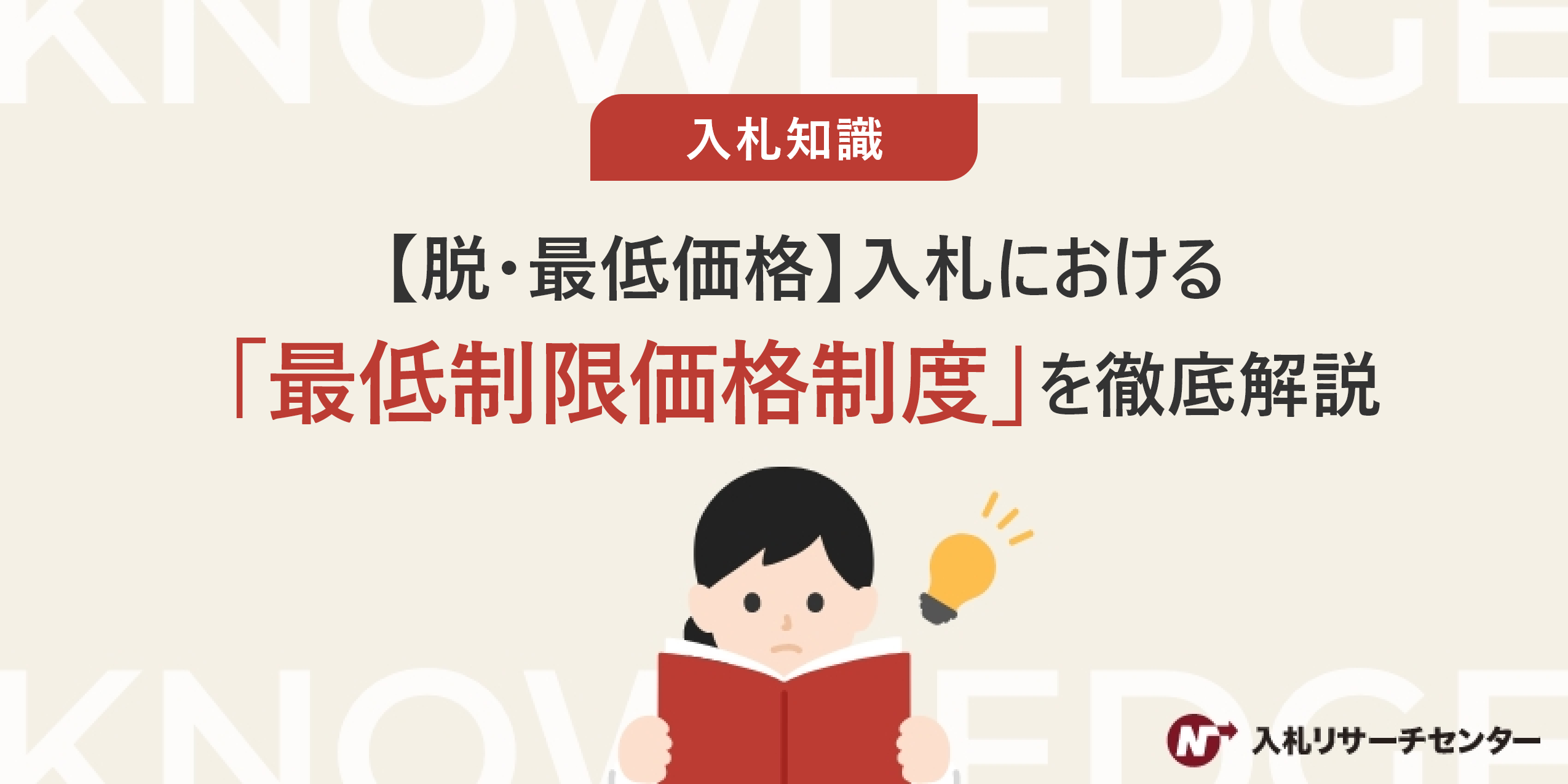





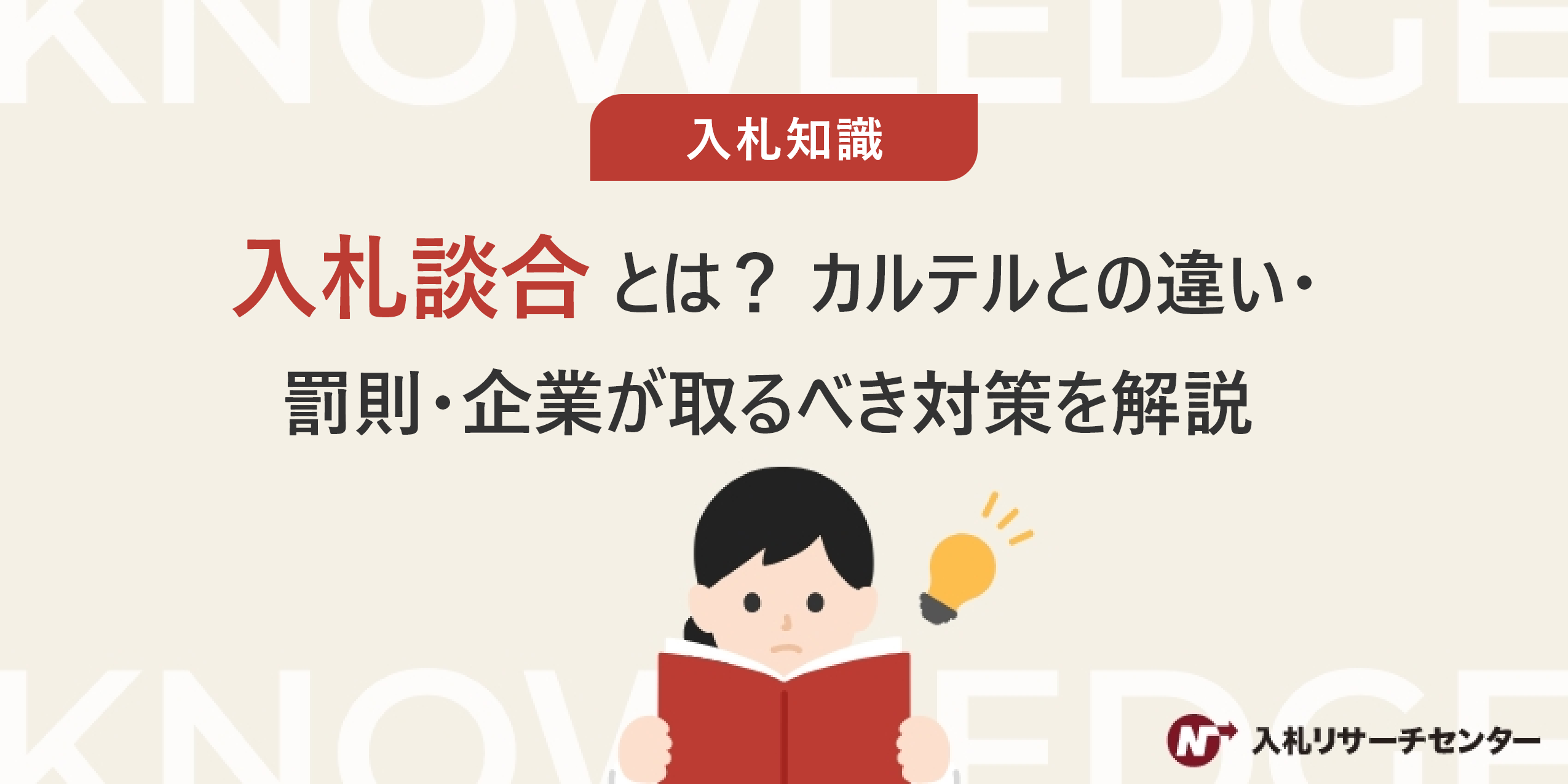
アイキャッチ.png)
.png)
.png)


