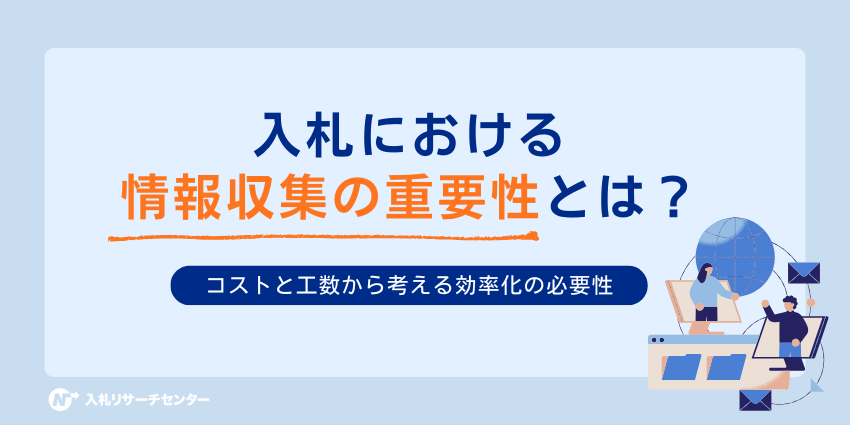限定された企業のみが参加できる入札方式のひとつに「指名競争入札」があります。しかし、その名称を聞いたことがあっても、具体的な参加条件や入札プロセスを把握しきれていないのではないでしょうか。
本記事では、入札に関心はあるものの、手続きの複雑さから難しさを感じている方に向けて、指名競争入札の概要をまとめました。
指名競争入札の基本概念や一般競争入札との違い、種類、メリット・デメリットなどをわかりやすく解説します。指名競争入札の制度の全体像を把握し、自社の入札戦略に役立てたい方はぜひ最後までご覧ください。
▶ 入札で新しい販路を開拓したい企業の方へ
のべ3,000社以上の相談実績と、NJSS運営16年以上の知見で
入札参入から落札ノウハウまで、入札アドバイザーがサポートします。
▶ 調達業務を効率化したい発注機関担当者の方へ
全国の自治体をはじめ9,000以上の官公庁が公示する調達情報の検索・閲覧が可能。
情報収集・仕様書作成・業者選定など日々の業務を大幅に効率化できます。
指名競争入札とは?
指名競争入札とは、発注機関が事前に選定した事業者のみが参加できる入札方法のことです。
発注機関である国や地方公共団体が、実績や技術力を備えた企業を指名し、限定的な競争のもとで入札が行われます。
この方式では、発注機関が「信頼性や実績のある事業者」と判断した企業のみが入札に参加できる点が特徴です。そのため、参加資格を得るには、過去の実績や技術力が重要な要素となります。
一般的な入札においては、広く事業者を募る一般競争入札が主流ですが、指名競争入札は以下のようなケースで採用されます。
- 過去の実績や技術力を持つ企業を指名したいとき
- 小規模な案件
- 競争性が低い案件
- 不誠実な事業者の参加を避けたい場合
たとえば、防鳥ネットの修繕やお祭り開催期間のゴミ収集業務など、小規模な案件で指名競争入札が採用されることがあります。また、技術力が求められる案件としては、橋梁の補修工事や歴史的建造物の修繕などが挙げられます。
これらの案件では、専門的な知識や高度な施工管理が必要とされるため、豊富な実績を持つ技術力の高い事業者が選定される傾向にあります。
このように指名競争入札は、一般競争入札の実施が困難な特殊なケースで用いられる方式です。
一般競争入札との違い
一般競争入札と指名競争入札の違いは、入札の公開範囲にあります。
一般競争入札とは、不特定多数の事業者が参加できるオープンな入札方式のことです。発注機関は、最も有利な条件を提示した事業者と契約するため、公平性や競争性が高い点が特徴です。
ただし、すべての事業者が無条件で参加できるわけではなく、「建設業許可を受ける」など、一定の要件を満たすことが必要なケースもあります。
一般競争入札の中には、発注機関が定めた参加要件を満たした企業のみが入札できる「制限付一般競争入札」という方式もあります。指名競争入札と類似していますが、指名競争入札のように発注機関が特定の企業を選定するのではなく、要件を満たせば参加できる点が異なります。
入札案件が公開され、一般に知らされることを「公告」、または「公示」と言います。公告・公示の前には、官公庁内部で案件に関する仕様の検討や仕様書の作成が準備として行われています。
官公庁内部の準備段階の情報をいち早く察知し営業活動に落とし込むためには、予算や計画を把握できるGoSTEPのようなツールを活用するのも手段のひとつと言えるでしょう。
指名競争入札の種類
指名競争入札には複数の種類があり、入札までの流れや主に活用される分野が異なります。そのため、各種類の違いを正しく把握することで、自社の活動に適した入札方式を選択しやすくなるでしょう。
指名競争入札の種類として、下記の3つが挙げられます。
- 公募型指名競争入札
- 簡易公募型指名競争入札
- 工事希望型指名競争入札
それぞれの特徴について詳しく解説します。
関連記事:【官公庁入札の種類】主な入札方式と、それぞれのメリット・デメリット
種類1.公募型指名競争入札
指名競争入札の種類のひとつ目は、公募型指名競争入札です。
公募型指名競争入札とは、発注機関が提示した条件を満たした事業者が、参加の意向を示す入札方式です。
入札の流れは、はじめに事業者が発注機関に技術資料を提出します。発注機関は技術資料をもとに事業者の審査を実施し、適格と判断された事業者へ指名通知書を送付します。
その指名通知書が届いた事業者だけが、競争入札へ参加が可能です。
種類2.簡易公募型指名競争入札
指名競争入札の種類のふたつ目は、簡易公募型指名競争入札です。
簡易公募型指名競争入札の一般的な流れは、公募型指名競争入札と同様です。まず発注機関が提示した条件をクリアした事業者が参加意向を示す書類を提出します。
公募型指名競争入札と異なる点は、小規模な業務の入札に採用される点です。小規模のため参加者も厳選している場合が多く、入札手続きも簡略化される傾向にあります。
種類3.工事希望型指名競争入札
指名競争入札の種類の3つ目は、工事希望型指名競争入札です。
工事希望型指名競争入札は、公募型や簡易公募型とは異なり、事業者が自ら参加を希望する仕組みではありません。
発注機関である国や地方公共団体が、特定の条件にもとづいて直接指名するため、参加するハードルは高いといえるでしょう。工事希望型指名競争入札は主に、専門性の高い工事案件などで、採用されるケースが多いのが特徴です。
指名競争入札のメリット
一般競争入札のほうが参加の敷居が低く、公平性が確保されやすい方式ですが、指名競争入札に参加するメリットは一体どのようなものでしょうか。ここでは、指名競争入札のメリットを3つ紹介します。
- 落札される可能性が高くなる
- 官公庁と長期的に良好な関係を築ける
- 価格競争になりにくい
メリット1.落札される可能性が高くなる
指名競争入札のメリットのひとつ目は、落札の確率が向上する点です。
一般競争入札では、不特定多数の事業者が参加するため競争が激化し、落札の難易度が上がります。一方、指名競争入札では、発注機関から指名を受けた事業者だけが入札に参加できるため、競争相手が限定され、相対的に落札の可能性が高くなります。
落札につながりやすい入札に集中できる点は、指名競争入札のメリットといえるでしょう。
メリット2.官公庁と長期的に良好な関係を築ける
指名競争入札のメリットのふたつ目は、官公庁と長期的に良好な関係を築ける点です。
指名競争入札で指名を受けることは、官公庁から実績や技術力を認められた証明ともいえます。
一度指名された事業者は、別の案件でも指名を受ける可能性が高まり、継続的な受注につながりやすいのも特徴です。誠実な対応を繰り返すことで、官公庁との長期的な信頼関係を構築することにつながるでしょう。
発注機関との安定した関係を構築できる点が、指名競争入札のメリットです。
とはいえ、発注機関との初回の接点を持ち、関係構築を行うことは容易いことではありません。発注機関側の意思決定の流れやスケジュールを把握した上で営業活動を行うことが重要になります。予算や計画を把握できるGoSTEPのようなツールを活用し、高度な営業活動をできるようにしましょう。
メリット3.価格競争になりにくい
指名競争入札のメリットの3つ目は、価格競争になりにくいことです。
一般競争入札の場合は、最もよい条件を提示した事業者が落札するケースがほとんどです。そのため最終的な落札者を決めるときには、どうしても価格競争に陥りやすい傾向にあります。
一方、指名競争入札では、参加事業者が限定されるため価格競争が起こりにくく、適正な価格での受注が期待できます。
また、指名競争入札では、発注機関が求める技術力や品質基準を満たすことが重視されるため、単純な価格勝負ではなく、企業の強みを活かした競争がしやすくなる点もメリットといえるでしょう。
指名競争入札のデメリット
指名競争入札には、一般競争入札にはないデメリットも存在します。ここでは特に留意すべき指名競争入札の2つのデメリットについて解説します。
- 発注機関に指名されないと入札に参加できない
- 透明性や公正性が低い
リスクを正しく把握したうえで対策を講じることで、指名競争入札での落札率を向上させましょう。
デメリット1.発注機関に指名されないと入札に参加できない
指名競争入札のデメリットのひとつ目は、発注機関に指名されないと入札に参加できない点です。
指名競争入札では、発注機関からの指名がなければ入札に参加することはできません。
官公庁のような発注機関から評価されたうえで、指名されなければならないためハードルが高い入札方式といえるでしょう。
そのため、十分な実績や技術力がある企業であっても、必ずしも入札に参加できるとは限らない点がデメリットです。
とくに新規参入の事業者にとっては、過去の実績や信頼関係が不足しているため、指名を受けにくくなる傾向にあります。短期的な成果だけでなく、長期的な実績や通常よりも高い技術力が求められるでしょう。
デメリット2.透明性や公正性が低い
指名競争入札のデメリットのふたつ目は、透明性や公正性が低い点です。
指名競争入札では、一般競争入札に比べると発注機関が事前に落札候補を想定しているケースもあります。そのため価格競争になりにくい一方で、評価基準が不明瞭になることもあります。
また、選定基準が明確でない場合、落札できなかった際に原因分析や次回に向けた対策を立てにくい点もデメリットのひとつです。
不透明な理由で落札できない場合もあるため、落札結果に対する透明性や公正性の確保が課題となることもあるでしょう。
指名競争入札の流れ
指名競争入札が実施される場合、どのような流れで進めていくのでしょうか。一般競争入札とは異なり、官公庁などの発注機関から通知が届く点が指名競争入札の特徴です。
ここでは、指名競争入札の一般的な流れを下記の5つのステップに分けて解説します。
- 発注機関で資格審査
- 発注機関から事業者に入札参加の通知が届く
- 入札する
- 落札する
- 契約する
1.発注機関で資格審査
指名競争入札では、まず発注機関での資格審査を通過しなければなりません。一般競争入札と同様に、発注機関ごとに競争入札参加資格審査を申請し、審査に合格することで有資格者名簿に登録されます。
たとえば建設業の場合は、建設業の許可を取得したうえで「経営事項審査(経審)」を受ける必要があります。この結果にもとづき企業の評価が行われ、格付けが決定されるため、入札資格の取得には重要なプロセスとなります。
2.発注機関から事業者に入札参加の通知が届く
資格審査を通過すると、発注機関から事業者に対して、入札参加の通知が送られます。
発注機関が指名競争入札する際には、業者選定委員会などを経てから、一定の基準を満たす事業者を指名する流れとなります。
指名する業者の数は、国の機関では「原則として10人以上」、地方自治体の場合は、各自治体の規則で定められています。
| (競争参加者の指名) 第九十七条 契約担当官等は、指名競争に付するときは、第九十五条の資格を有する者のうちから、前条第一項の基準により、競争に参加する者をなるべく十人以上指名しなければならない。 2 前項の場合においては、第七十五条第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。 (引用:e-Gov法定検索「予算決算及び会計令 第97条第1項」) |
指名される事業者の基準は、発注機関のホームページなどで公開されているため、事前に確認しておきましょう。指名基準の例は、経営状態や技術者の保有資格数、手持ち工事の量と在籍技術者数、施工実績などです。
さまざまな要件を総合的に考慮したうえで、指名するかの判断が下されます。
3.入札する
指名通知を受け取った事業者は、指名競争入札へ参加が可能です。
ただし、指名を受けた事業者は必ずしも参加する義務があるわけではありません。事業者は、自社の状況や戦略に応じて参加の可否を決められます。
参加を決定した場合は、発注機関に対して正式に回答を提出します。入札への参加は慎重に検討し、事業のリソースや採算性を考慮したうえで判断しましょう。
4.落札する
指名競争入札の落札までの流れは、一般競争入札と同様です。
入札に参加すると回答した事業者の中から、発注機関が最も適した事業者を選定し、落札者を決定します。
発注機関にとって、もっとも有利な条件を提示した事業者が選ばれるのが一般的です。発注機関の意図を的確に汲み取り、適切な条件を提示するよう心がけましょう。
5.契約する
落札者が決定すると、発注機関と事業者の間で契約が締結されます。
契約手続きに入る前に、発注機関が公開する情報や契約の流れを十分に確認しておきましょう。
発注機関によっては、細かいルールが異なる場合もあるため、スムーズな契約締結に向けた準備を進めましょう。
指名競争入札についてよくある質問
指名競争入札のメリット・デメリットを把握したうえで、さらに詳しく知りたいポイントもあるでしょう。ここでは、指名競争入札に関するよくある3つの質問を解説します。
- 指名競争入札が1者のみの場合は有効?
- 随意契約と指名競争入札の違いは?
- 指名競争入札を辞退することは可能?
指名競争入札についての理解を深めることで、スムーズに入札の手順を踏めるようになるでしょう。
指名競争入札が1社のみの場合は有効?
指名競争入札において、1社のみが入札した場合、その入札は基本的には無効です。
1社入札とは、入札の際に競争相手が存在しない状態のことを指します。指名競争入札では、発注機関が複数の事業者を選ぶことが多いため、1社のみが参加するケースは稀です。
万が一、1社しか参加しない場合は、発注機関の選定方法を見直す必要があるでしょう。
一方、一般競争入札の1社入札については現状、会計法令上明確な規定がありません。そのため、例外的に1社入札になるケースもあります。
これは、1社入札を無効とすると、再度参加者を募っても事業者が集まらない可能性があるためです。そのため、発注機関が必要と判断した場合は、1社入札でも有効とするケースがあります。
指名競争入札と随意契約の違いは?
指名競争入札と随意契約は、その形態が大きく異なります。随意契約は契約形式であり、一般競争入札・指名競争入札は入札方式の1種です。
随意契約とは、国・地方公共団体などの公共機関が発注する際に、特定の受注者を選定して契約を結ぶ方式です。ただし、発注機関が自由に選べるわけではなく、法律やルールにもとづいて適用条件が厳格に定められています。
一方、指名競争入札は、発注機関が複数の事業者を選定したうえで、競争を通じて契約先を決定する仕組みです。
一般的に、公共機関が発注を行う際は入札が実施されるため、随意契約はあくまで例外的な対応といえます。
指名競争入札を辞退することは可能?
指名競争入札の辞退は、申し出るタイミングによって可否が異なります。
基本的に「指名通知から入札書の提出前」または「再入札の告知から入札書の提出前」であれば辞退が可能です。しかし「入札書提出から開札」「落札から契約」の段階まで進んでしまうと、原則として辞退はできません。
辞退を検討する際は、速やかに発注機関へ連絡し、必要な手続きを進めましょう。
指名競争入札を上手に活用して落札の可能性を高めよう
指名競争入札とは、発注機関が入札に参加できる事業者を指名したうえで入札する方式のことです。
不特定多数の事業者が参加する一般競争入札と違い、競合が少ないため落札される可能性が高くなるでしょう。過剰な価格競争になりにくいなど、さまざまなメリットがあります。
参加までのハードルは高いものの、一度参加できれば長期的に発注機関とよい関係を築けるでしょう。事業者の方は、ぜひ指名競争入札を活用してみてください。
▶ 入札で新しい販路を開拓したい企業の方へ
のべ3,000社以上の相談実績と、NJSS運営16年以上の知見で
入札参入から落札ノウハウまで、入札アドバイザーがサポートします。
▶ 調達業務を効率化したい発注機関担当者の方へ
全国の自治体をはじめ9,000以上の官公庁が公示する調達情報の検索・閲覧が可能。
情報収集・仕様書作成・業者選定など日々の業務を大幅に効率化できます。






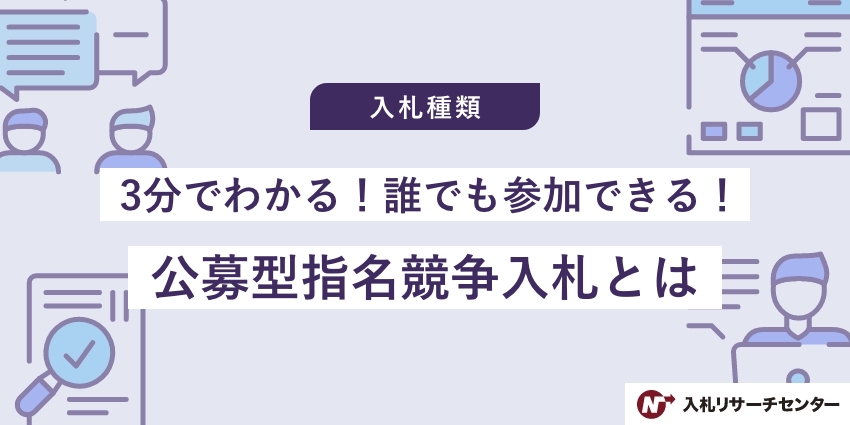
アイキャッチ.png)
.png)
.png)