随意契約とは、国や地方自治体が特定の企業と直接契約を結ぶ方式のことです。
公共事業では、一般競争入札を行うのが一般的です。しかし、特定の条件を満たせば随意契約が認められる場合があります。
本記事では、随意契約の概要や一般入札との違い、メリット・デメリット、案件を獲得するためのポイントを解説します。官公庁・自治体との取引拡大を目指す企業や、入札制度を正しく理解したい方は、ぜひ参考にしてください。
入札アカデミー(運営:株式会社うるる)では、入札案件への参加数を増やしていきたい企業様向けの無料相談を承っております。
のべ3,000社以上のお客様に相談いただき、好評をいただいております。入札情報サービスNJSSを16年以上運営してきた経験から、入札案件への参加にあたってのアドバイスが可能です。
ご相談は無料となりますので、ぜひお問い合わせください。
随意契約とは?
公共機関が行う契約の中でも、随意契約は「例外的に競争を行わず契約を締結できる方式」です。
ここでは、随意契約の基本的な仕組みと法的な位置づけについて解説します。
競争入札を行わず契約相手を選定する契約方式
随意契約とは、国や地方自治体が競争入札を行わずに、特定の企業と直接契約を結ぶ方式です。企画競争入札も、随意契約の一種に含まれます。
通常、公共機関が発注を行う際は、原則として入札を実施し、公正な競争のもとで契約先を決定しなければなりません。しかし、「予算決算及び会計令」や「地方自治法施行令」にもとづき、一定の条件下では随意契約が認められています。
以下の記事では、入札の基本情報について詳しく解説しているため、あわせて参考にしてください。
関連記事:入札とは?入札の基本情報・入札参加の流れをわかりやすく解説
一般競争入札・指名競争入札との違い
既存記事「一般競争入札・指名競争入札との違い」の内容を流用
それぞれの違いを簡単に比較できるように表を入れる予定です。
入札は、国や地方自治体が発注を行う際に活用する契約の仕組みです。複数の民間企業に競争の機会を与え、その中からもっとも有利な条件を提示した事業者を選定します。
代表的な方式が一般競争入札と指名競争入札であり、それぞれの特徴は下記のとおりです。
| 種類 | 特徴 |
| 一般競争入札 | すべての事業者が参加可能で、もっとも多くの公共工事や発注案件で採用されている |
| 指名競争入札 | 事前に選ばれた特定の企業のみが入札に参加できる |
一般競争入札は、公平性・透明性を重視して行われるのが基本であり、多くの公共案件で採用されています。
随意契約は、発注機関が特定の企業を選定し、競争入札を行わずに直接契約を結ぶ方式です。ただし、すべての案件で適用されるわけではありません。競争入札による選定が困難な場合に限り、随意契約が認可されます。
また、一般競争入札や指名競争入札では、参加資格や等級などの要件を満たす必要があります。
随意契約は、発注機関の判断により契約相手が決まるため、柔軟な対応が可能です。なお、競争が行われないため、透明性の確保が求められます。
企業が随意契約を獲得するためには、まず一般競争入札や指名競争入札で実績を積み、発注機関からの信頼を得ることが重要です。
一般競争入札と指名競争入札の違いについて、以下の記事で詳しく解説しているため、ぜひ参考にしてください。
関連記事:一般競争入札と指名競争入札の違いとは?メリットやデメリットも解説
随意契約の種類
随意契約は、おもに下記4種類に分けられます。
- プロポーザル方式
- 特命随意契約
- 少額随意契約
- 不落随意契約
それぞれの特徴を解説します。
プロポーザル方式
プロポーザル方式とは、不特定多数の事業者に対し、テーマに沿った企画書・提案書を提出させ、もっとも優れた提案をした企業と契約を結ぶ方式です。
一般競争入札のように価格の安さを基準とするのではなく、提案内容の質や実現可能性が評価のポイントとなります。
プロポーザル方式には、公募型と指名型の2種類があります。
| 種類 | 特徴 |
| 公募型 | 国・省庁や地方自治体のサイトに入札情報を掲載し、広く企業から提案を募集する方式 |
| 指名型 | あらかじめ選定された企業のみ入札に参加し、プロポーザルを行う方式 |
プロポーザル方式は法律上、随意契約の一種に分類されます。
ただし、一般的な随意契約のように、発注者が契約先を自由に選ぶのではありません。提案内容を審査したうえで選定するため、公正性を一定程度確保できるのが特徴です。
また、契約の柔軟性が高く、条件交渉が不調となった場合には次点の提案者と契約交渉を行えます。
こうした特徴から、プロポーザル方式は官公庁だけでなく、民間の契約でも採用されるケースが増えています。
プロポーザルと一般競争入札の違いについて、以下の記事で詳しく解説しているため、ぜひ参考にしてください。
関連記事:プロポーザルと一般競争入札の違いをわかりやすく解説!落札のためのポイントもご紹介
特命随意契約
特命随意契約は、発注機関が競争入札を行わず、特定の業者を直接指名して契約を締結する方式です。一般的な随意契約は、この特命随意契約を指します。
おもに、下記のようなケースで適用されます。
- 特定の技術やノウハウが必要な場合
- 緊急性が高く、入札を行う時間的余裕がない場合
随意契約は、例外的な契約方式ため、制度を厳格に運用することが大切です。多くの地方自治体では、特命随意契約のガイドラインを策定し、適用範囲を明確にしています。
さいたま市の「随意契約ガイドライン」では、随意契約の内容について細かな記載がありました。
【ガイドラインの主な内容(目次抜粋)】
|
特命随意契約は、特定の条件下でのみ適用される契約方式です。そのため、発注機関の裁量による不透明な運用を防止するルールが重要視されています。
少額随意契約
少額随意契約とは、契約金額が一定額以下の場合に限って随意契約が認められる方式です。金額の上限基準は「地方自治法施行令」に定められており、自治体の規模によって基準が異なります。
少額随意契約では、2社以上の業者から見積もりを取得し、その中から最適な事業者を決めます。一定の競争性を確保しつつ、手続きの簡素化を図れる点が特徴です。
ただし、上限額を超える場合は、原則として競争入札を行う必要があります。
特命随意契約のように発注機関が1社を直接指定する方式とは異なり、ある程度の公平性が保たれる仕組みです。
不落随意契約
不落随意契約とは、入札の結果として落札者が決定しなかった場合に、発注機関が随意契約を締結する方式です。具体的なケースは、下記のとおりです。
- 入札に参加する事業者が1社もいなかった場合
- 最低入札額が予定価格を上回り(入札不落)、落札者が決定しなかった場合
- 落札者が契約を辞退し、契約不成立となった場合
通常、このような状況では、3回程度の再入札が実施されます。しかし、それでも落札者が決まらない場合に限り、不落随意契約が適用されます。
この場合、最低価格を提示した事業者と交渉を行い、適正な価格で合意が得られれば契約成立です。
ただし、発注機関の裁量が入るため、適用の際には透明性の確保が求められます。
適用条件は「予算決算及び会計令 第99条」によって、明確に定められています。
| 第九十九条の二 契約担当官等は、競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がないときは、随意契約によることができる。この場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
九十九条の三 契約担当官等は、落札者が契約を結ばないときは、その落札金額の制限内で随意契約によることができる。この場合においては、履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。
|
不落随意契約は、通常の競争入札において、適切な受注者が見つからなかった場合に限り適用可能です。随意契約の中でも、とくに例外的な契約とされています。
以下の記事では、入札不調と不落随契の違いについて解説していますので、あわせてご覧ください。
随意契約が認められる条件
随意契約の条件は、「地方自治法施行令」と「地方公営企業法施行令」で定められています。
詳細は、下表のとおりです。
| 項目 | 条件 |
| 1号 | 売買や貸借、請負契約などの契約で、一定額を超えない場合 |
| 2号 | 不動産の買入れ・借入れや、普通地方公共団体が必要とする物品の製造・修理・加工 または納入に使用させるために必要な物品の売払い、その他の契約で競争入札では適切な事業者が見つかりにくい場合 |
| 3号 | 特定の施設や機関からの購入・役務の提供を受ける場合 |
| 4号 | 新規事業分野のベンチャー企業から、新しい商品を購入する場合 |
| 5号 | 災害復旧や突発的な業務など、競争入札を実施する時間的余裕がない場合 |
| 6号 | 競争入札を行うことで発注条件が悪化する恐れがある場合 |
| 7号 | 市場価格と比較して著しく有利な条件で契約できる見込みがある場合 |
| 8号 | 入札を実施したが、応札者がいなかった、または落札者が決まらなかった場合 |
随意契約はこれらの条件を満たす場合に限って実施されます。随意契約を活用するためには、それぞれの条件を理解し、発注機関の要件を満たす必要があります。
以下の記事では、随意契約の入札参加資格について詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
関連記事:随意契約の入札参加資格について
【2025年度改正】少額随意契約の基準額引き上げ
2025年(令和7年)4月1日から、額随意契約(少額随契)の基準額が約50年ぶりに改正されました。物価上昇や人手不足などによって、従来の基準が実態に合わなくなっていたことを受けて、調達の効率化と行政負担の軽減を目的としたものです。
背景には、建設資材や人件費の高騰によって「少額」とされる範囲が実情とかけ離れていたこと、入札手続きに要する時間とコストが自治体の負担となっていたことがあります。これにより、調達を柔軟かつ迅速に行える仕組みへの転換が進められました。
改正前後の基準額を、下表にまとめています。
| 契約の種類 | 国・都道府県・政令市
【現行】 |
国・都道府県・政令市
【改定後】 |
政令市を除く市区町村
【現行】 |
政令市を除く市区町村
【改定後】 |
| 工事・製造 | 250万円 | 400万円 | 130万円 | 200万円 |
| 財産の買い入れ | 160万円 | 300万円 | 80万円 | 150万円 |
| 物件の借り入れ | 80万円 | 150万円 | 40万円 | 80万円 |
| 財産の売り払い | 50万円 | 100万円 | 30万円 | 50万円 |
| 物件の貸し付け | 30万円 | 50万円 | 30万円 | 30万円 |
| その他 | 100万円 | 200万円 | 50万円 | 100万円 |
今回の見直しは、単なる金額の変更にとどまらず、自治体の契約制度や発注方式そのものを見直す契機となっています。
事業者にとっても、新基準にあわせた見積りの対応や提案体制の整備が重要になるでしょう。
以下の記事では、少額随意契約の基準額引き上げの内容や、受注拡大のポイントをわかりやすく解説しています。あわせて参考にしてください。
関連記事:少額随意契約とは?基準額引き上げの内容・受注拡大のポイントを解説
【発注機関側】随意契約のメリット・デメリット
ここでは、発注機関側から見た随意契約の主なメリットとデメリットを解説します。
| メリット | デメリット |
|
|
メリット
発注機関側にとっての随意契約のメリットは、下記のとおりです。
- 実績のある企業と契約できるため、品質・信頼性を確保しやすい
- 手続きが簡素で契約までがスムーズになる
- 事務負担やコストを削減できる
- 競争入札に比べて柔軟な対応がしやすい
随意契約は、迅速な契約締結や業務効率化につながる点がメリットです。
限られた職員体制や短期間での事業遂行が求められる場合に、発注機関がスピーディに契約を進める手段として有効です。
デメリット
発注機関側にとっての随意契約のデメリットは、下記のとおりです。
- 公正性・透明性の確保が難しい
- 高額な契約になるリスクがある
- 住民への説明責任が生じる
随意契約は制度上、競争入札の「例外的な契約方式」と位置づけられています。
契約の合理的な理由や価格の妥当性を示さなければ、監査や住民からの指摘を受けるおそれがあります。発注機関は、契約理由を明確に記録し、透明性の高い手続きを維持することが重要です。
【事業者側】随意契約のメリット・デメリット
ここでは、事業者側の立場から見た随意契約のメリットとデメリットを解説します。
| メリット | デメリット |
|
|
メリット
事業者側にとっての随意契約のメリットは下記のとおりです。
- 入札準備の手間を省ける
- 競争に左右されず契約できる場合がある
- 技術力や実績を評価されやすい
- 発注機関との継続的な関係を築きやすい
随意契約は、入札にかかる時間やコストを削減しつつ、自社の技術・実績を直接評価してもらえる点が特徴です。
価格競争に依存せず、信頼関係をもとに安定的な取引を行いやすい契約形態といえます。
デメリット
事業者側にとっての随意契約のデメリットは次のとおりです。
- 発注機関に選ばれなければ契約機会がない
- 競争がない分、契約条件が発注機関に有利に設定されやすい傾向がある
- 発注先への依存リスクがある
- 随意契約は例外的な制度なため、案件数が限られる
随意契約は、発注機関から選定されることで、はじめて契約の機会が生じます。契約の主導権は発注側にあるため、条件交渉の余地が限られる点も特徴です。
また、制度上の適用範囲が狭いため、随意契約だけに依存せず、競争入札やプロポーザル方式と併用して事業機会を広げることが重要です。
随意契約の流れ
随意契約は、契約の種類によって進め方が異なります。ここでは、オープンカウンター方式による随意契約の流れを、解説します。
- 発注機関から見積書の作成・提出依頼
- 発注機関による見積もり合わせ
- 国・地方自治体が発注先を決定
- 契約の締結
それぞれチェックしていきましょう。
1.発注機関から見積書の作成・提出依頼
まず、発注機関から、随意契約を依頼したい旨の連絡を受けます。「地方自治法施行令」にもとづくオープンカウンター方式では、2社以上の事業者から見積もりを取得することが求められます。
オープンカウンター方式は「公募型見積合わせ」とも呼ばれており、公募形式で広く見積もりの提出を募り、契約相手を決定する方式のことです。
発注機関の調達ポータルや公式サイトを通じて案件を確認し、自社が対応可能かを判断しましょう。なお、1社のみを対象とした随意契約の場合、発注機関からメールやFAXで直接依頼が届くケースもあります。
以下では、オープンカウンター方式について詳しく解説していますので、あわせて参考にしてください。
2.発注機関による見積もり合わせ
案件内容を確認し、指定されたフォーマットにしたがって、正確な見積書を作成して提出します。記載漏れや押印不備、封入方法の誤りがあると無効となる場合があるため、提出前に必ずチェックしましょう。
受け取った見積書をもとに、発注機関による選定が行われます。
見積書の作成期間は案件によって異なりますが、一般的には1週間から3週間程度とされています。見積書を提出する際には、余裕をもって準備し、期限を守ることが大切です。
3.国・地方自治体が発注先を決定
発注機関は、提出された見積書を比較し、適正な価格であるかを確認したうえで、発注先を決定するのが一般的な流れです。
各地方自治体が定めている随意契約のガイドラインでは、もっとも安い価格で見積もりを提出した方を、受注者に選定することが原則とされています。ただし、価格以外の理由で選定する場合は、第三者が納得できる説明を求められることもあります。
受注を獲得するには、競合他社の動向を踏まえて適正な価格を提示することが重要です。
4.契約の締結
発注機関が受注企業を決定したあと、契約条件の最終確認を行います。契約内容に問題がないかを慎重に確認し、必要に応じて調整を行いましょう。
最終的な契約条件に合意が得られれば、契約書の作成と契約に進みます。手続きは、通常の企業間契約と基本的に同じ流れで行われます。
契約締結後は、契約内容にもとづいて業務を遂行しましょう。
随意契約で案件獲得を目指すポイント
随意契約が認められるためには、下記のポイントを押さえることが大切です。
- 実績をつくる
- 発注機関に営業を行う
- 発注機関の課題感や動向を掴む
詳しく解説します。
実績をつくる
随意契約は、発注機関が「信頼できる事業者」と判断した企業にのみ発注されます。そのため、過去の実績がない企業が、突然契約を獲得する可能性はゼロに等しいです。
発注機関は、企業の業務遂行能力や過去の取引履歴を重視します。まずは競争入札に参加し、少しずつ実績を積み上げましょう。
一般競争入札での受注経験があれば、発注機関からの信頼を得やすくなり、継続的な取引や随意契約の可能性が高まります。小規模な案件から受注して、納期や品質を確実に守り、随意契約の候補に選ばれる可能性を高めましょう。
発注機関に営業を行う
随意契約は、発注機関が直接契約相手を選定するため、発注機関との関係構築が案件獲得のポイントになります。自社の強みや過去の実績をアピールし、信頼関係を築ければ、契約獲得のチャンスを広げられるでしょう。
ただし、繁忙期や年度末などに過度な営業を行うと、かえって印象を損ねるおそれがあります。発注機関の予算編成スケジュールや年度計画を事前に把握し、適切なタイミングで営業を行いましょう。
以下の記事では、国(省庁)・地方自治体への営業のかけ方について詳しく解説しています。適切な方法で営業活動を行いたい方は、ご参考ください。
関連記事:国(省庁)・地方自治体への営業のかけ方
発注機関の課題感や動向を掴む
随意契約の獲得には、発注機関の課題やニーズをどれだけ正確に把握できるかが大きく影響します。
単に営業を行うだけでなく、「どの部署が、どのような課題を抱えているのか」「今後どの分野に予算が割かれるのか」といった情報を分析しましょう。
また、発注機関の予算計画や政策方針を事前に調査し、適切なタイミングでアプローチを行うことも効果的です。
たとえば「GoSTEP」では、官公庁の予算情報を分析し、随意契約の可能性が高い案件を効率的に見つけられます。発注機関のニーズを先取りし、適切な提案を行うことで、随意契約のチャンスを広げられるでしょう。
効果的に随意契約を狙いたい企業・ご担当者様は、「GoSTEP」を活用してみてください。
以下の記事では、自治体ニーズを先取りする方法や政府の予算について詳しく解説していますので、あわせてご参考ください。
関連記事
自治体ニーズを先取り!効果的なアンケートで入札前に差をつける営業手法とは?
政府の予算ってどうやって決まる?スケジュールから逆算して積極型の案件提案へ
まとめ:随意契約を正しく理解してチャンスを広げよう
随意契約とは、競争入札を行わずに、発注機関が特定の企業と直接契約を結ぶ方式です。
契約までの手続きが簡素でスピーディに進む一方、公正性や透明性の確保が求められるため、適用には慎重な判断が必要です。
随意契約を獲得するためには、実績の積み上げや発注機関との信頼関係の構築などが欠かせません。発注機関の動向を理解し、最適なタイミングで提案を行うことで、契約獲得のチャンスを広げられます。
「入札アカデミー」では、入札や随意契約に関する疑問や悩みについて、専門アドバイザーが丁寧にサポートしています。入札の基本を学びたい方から、落札率を高めたい企業まで、幅広い相談に対応可能です。
入札や随意契約の仕組みを理解し、効果的な営業戦略を立てたい方は、「入札アカデミー」の無料相談を活用しましょう。
入札アカデミー(運営:株式会社うるる)では、入札案件への参加数を増やしていきたい企業様向けの無料相談を承っております。
のべ3,000社以上のお客様に相談いただき、好評をいただいております。入札情報サービスNJSSを16年以上運営してきた経験から、入札案件への参加にあたってのアドバイスが可能です。
ご相談は無料となりますので、ぜひお問い合わせください。






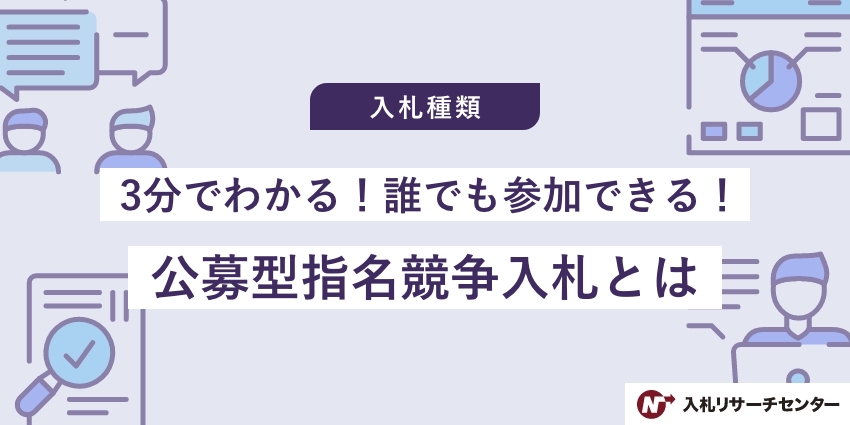
アイキャッチ.png)
.png)
.png)


