入札と聞くと複雑で難しそうだと思い、参加をためらっていませんか?
入札方法や手順はいくつかありますが、どの案件も基本の流れは同じですので、一度経験すれば自信をもって入札に参加できるようになるでしょう。
本記事では、自治体の入札における流れや種類について解説します。また、入札が行われる目的や企業にもたらすメリットなどについて、これから入札を始めたい方にもわかりやすく説明しますので、ぜひ参考にしてください。
▶ 入札で新しい販路を開拓したい企業の方へ
のべ3,000社以上の相談実績と、NJSS運営16年以上の知見で
入札参入から落札ノウハウまで、入札アドバイザーがサポートします。
▶ 調達業務を効率化したい発注機関担当者の方へ
全国の自治体をはじめ9,000以上の官公庁が公示する調達情報の検索・閲覧が可能。
情報収集・仕様書作成・業者選定など日々の業務を大幅に効率化できます。
自治体の入札とは業務を依頼する企業を選定する手段
自治体の入札とは、自治体が発注する公共事業の工事を請け負う企業や、自治体が使用する物品を供給する企業を、公平に選定するための仕組みです。
発注内容は、主に次のようなものがあります。
- 物品:デスクやパソコンなどの物品購入
- 役務:清掃や警備、運搬など、特定のサービス提供
- 建設工事:道路や建物などの建設、改修、修繕
- 建設コンサルタント・測量:建設における設計、監理、測量業務など
自治体による入札は公共入札とも呼ばれ、公共事業における業務や物品購入先は、そのほとんどが入札によって決められています。
関連記事:
公共工事の入札とは?種類や専門用語、参加するための資格を徹底解説
自治体による入札が行われる理由は公平性と透明性を守るため
自治体による入札が行われる主な理由は、公平性と透明性を守るためです。
入札は予定価格や条件の公開により、入札情報を事前に知ることが可能です。そのため、条件にあえば、どの企業でも公平な立場で入札に参加できるシステムとなっています。
また、入札後は、落札金額や落札者の情報が自治体HPや専用サイトで公開されます。公共事業の予算は税金で賄われているため、市民から不信感を抱かれてはいけません。
税金の使い方の透明性を高め、市民からの信頼を得るためにも、公共事業や物品の購入は入札によって金額や落札者が公開されているのです。
入札談合は犯罪行為
事前に公開されている入札情報について、企業同士で入札額を話し合い、決定する行為は入札談合と呼ばれ、法律違反です。
入札談合は不当な取引を制限するために、以下2つの法律で禁止されています。
- 刑法 第九十六条の六(公契約関係競売等妨害)により、3年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、又はその両方
- 入札談合等関与行為防止法により、5年以下の懲役か250万円以下の罰金のいずれか
入札談合は入札した段階ではなく、話し合いや電話、メールなどにより意思疎通が行われた時点で成立します。
入札談合は「公平性と透明性」が守られないため、決して行ってはいけない行為であることを認識しておきましょう。
参考:
e-Gov 法令検索 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令 」
e-Gov 「入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律」
関連記事:
入札談合とは?禁止理由やカルテルとの違いをわかりやすく解説!
自治体による入札に参加するメリットとデメリット
自治体への入札は安定した収益や長期的な仕事の確保につながりますが、厳しい価格競争や遵守すべき法的規則といった課題もあります。
入札に参加するメリットとデメリットについて、以下で詳しく確認しましょう。
メリット
入札は企業にとって利益が増えるだけでなく、「公共事業の成功」「自治体と取引している企業」などの理由から、信頼性の向上や企業の成長につながります。
自治体の主な資金である税金は、景気の変動による影響を受けないため、支払い遅延や不履行のリスクが低く、取引先としては安定しています。そのため契約期間中は、安定した収益が見込めるでしょう。
さらに長期契約であれば、期間中は安定的に業務と収益があるため、計画的な企業運営が可能です。
デメリット
入札は、事前に参加資格申請の提出が必要であったり、入札書類の作成があったりと、ある程度の知識がないと難しいと感じるかもしれません。
さらに入札方法によっては、提案書の作成やプレゼンテーションの準備など、入札書類作成以外の労力が必要になります。
一般競争入札では、価格競争が激化すると低利益になる場合があります。それだけでなく、無理な入札によって赤字になると企業運営にも影響を及ぼすため、予定価格と自社の予算内とでバランスのとれた適切な金額での入札を心がけましょう。
自治体の主な入札方法は3種類

自治体による主な入札方法は、以下の3種類があります。
- 一般競争入札:最もスタンダードな入札方法。条件があえばどの企業でも入札できる
- 指名競争入札:自治体が指名基準にもとづいて企業を指名。指名がなければ入札できない
- 随意契約:入札を行わず、発注者が事前に定めた条件にもとづき、契約先を選定する方法。見積書や企画書、提案書の提出などによる選出方法がある
3種類の入札方法について、以下で詳しく解説します。
関連記事:
【官公庁入札の種類】主な入札方式と、それぞれのメリット・デメリット
①一般競争入札
一般競争入札は、入札方法の中でも最もスタンダードな方法です。
事前に入札参加資格申請を提出しており、ランクなどの入札資格を有する企業であれば、どの企業でも参加できます。
一般競争入札において、落札者の選定は「最低価格落札方式」と「総合評価落札方式」の2種類です。
- 最低価格落札方式:価格によって企業を落札する方式
- 総合評価落札方式:価格以外にも、技術力や実績など複数の項目を総合的に判断して、落札する方式
一般競争入札におけるメリットとデメリットは、以下のとおりです。
| メリット | デメリット |
| ・参加資格、条件があえばどの企業でも参加しやすい ・公平性や機会均等の確保がしやすい |
・価格競争が激しい ・最低価格落札方式では、利益が出にくい |
一般競争入札は、これから入札の実績を積み重ねたい企業に適した入札方法です。
関連記事:一般競争入札と指名競争入札の違いとは?メリットやデメリットも解説
②指名競争入札
指名競争入札は、自治体が指名基準にもとづき複数の企業を指名して、その中で最も有利な条件を提示した企業が落札する入札方法です。
指名競争入札は、特定の専門性や条件に合った企業を選定し、適切な競争を促進できる点が特徴です。
しかし、指名競争入札は、一般競争入札に比べて談合が行われやすく問題視されているため、公平性の観点から案件は減少しているのが実情です。
落札者の選定方法は一般競争入札同様、「最低価格落札方式」と「総合評価落札方式」の2種類です。
指名競争入札には自治体が企業を指名する形のほかに、参加者を募集し、応募者の中から入札に参加できる企業を指名する「希望制指名競争入札」もあります。
公募型指名競争入札とも呼ばれ、指名競争入札と一般競争入札の中間のような入札方法です。
指名競争入札におけるメリットとデメリットは、以下のとおりです。
| メリット | デメリット |
| ・参加企業が限られるため、落札のチャンスが高くなる ・価格競争になりにくいため、利益が出やすい |
・指名がないと入札に参加できない ・公平性、透明性が低くなりやすい |
一度指名競争参加入札に指名されると、同様の規模の案件で再度指名を受ける可能性が高まるのもメリットのひとつでしょう。
関連記事:3分でわかる!誰でも参加できる!公募型指名競争入札とは
③随意契約
随意契約は「随契」とも呼ばれ、入札は行わずに自治体が法律やルールにもとづいて、適切な企業を選ぶ方法です。
過去に実績があったり、ほかに対象の事業者がいなかったりする場合に行われ、公共事業や物品購入の企業を決める方式としては例外的です。
ほかにも、随意契約には価格における競争性が強い「オープンカウンター」や、企画力で適した企業を決定する「企画競争入札」があります。
オープンカウンターは見積合わせとも呼ばれ、事前に見積り条件を公示し、提出された見積書の中から最も有利な条件を提示した企業を落札する方式です。
また、企画競争入札には、指定したテーマの企画書などの提出を求め、最も適した提案をした企業と契約する「プロポーザル方式」や「コンペ式」があります。
企画競争入札は主に、設計やコンサルタント業務など技術提案が重要な分野に加え、イベント運営、システム開発、広報戦略など、提案内容の質や創造性、技術力が重視される分野にも適用される入札方式です。
随意契約におけるメリットとデメリットは、以下のとおりになります。
| メリット | デメリット |
| ・随意契約に選ばれた場合、確実に受注できる ・競争がなく、契約までがスムーズ ・価格だけでなく企画や提案力が強みとなる案件がある |
・過去実績がないと選ばれにくい ・透明性の確保がしにくい ・必要書類の準備が大変に感じる可能性がある |
以上の特徴から、随意契約は技術力に自信のある企業に適している入札方式といえるでしょう。
関連記事:企画競争の流れ
自治体での入札の流れ5ステップ
本章では、3種類の入札方法から最もスタンダードな「一般競争入札」の流れを5ステップで解説します。
①入札参加資格を取得する
②入札情報をチェックし案件を探す
③仕様書を確認し、説明会に参加する
④入札をする
⑤契約をする
入札に参加するためには、単に入札書を提出するだけではなく、事前に入札参加申請を行い、参加資格を取得する必要があります。
入札で落札するためにも、事前に全体の流れをしっかりと確認しておきましょう。
①入札参加資格を取得する
入札に参加するには事前に、「入札参加資格」を取得する必要があります。自治体によっては事業登録や指名願いとも呼ばれます。
申請時期は自治体HPに掲載されますが、常に掲載されているわけではなく、申請時期が近づくと公開されることが一般的です。申請期間を逃さないよう、定期的にHPを確認しましょう。
分野や入札案件によって参加資格申請の提出方法や書類の内容が異なるため、自社の分野や案件にあった参加資格の申請が必要です。
申請書を期日までに提出すると自治体にて審査が行われ、等級が確定します。等級により参加できる入札案件の価格規模も決定されます。
なお、入札参加資格は一度取得すると、1~3年間の有効期限があります。有効期限が切れる前に更新手続きが必要のため、すでに資格を取得している場合は期限をチェックしましょう。
関連記事:【図解あり】入札参加資格の種類・等級・申請方法をわかりやすく解説|無料相談も受付中
②入札情報をチェックし案件を探す
入札参加資格を得たら、自治体のHPや入札情報サイトで入札参加できる分野の案件を探します。
入札案件の詳しい情報が公開されることを「入札公告」と呼び、国の入札規定により、入札期日の10日前までに公告されます。
参照:e-GOV法令検索「予算決算及び会計令」第74条
一般競争入札案件では、どの企業でも公告内容を見られる一方、指名競争入札は指名された企業だけが閲覧可能な場合があります。
また、入札の概要や入札方式、入札スケジュールが書かれている文書を「公示書(公告)」と呼び、記載内容に沿って入札が実施されます。
入札希望の案件と似た案件結果を参考に、入札の可否を検討しましょう。
過去の落札結果は、自治体HPで一定期間後に削除されることがあります。入札情報提供サービスには過去の案件情報が蓄積されているため、効率的な活用をおすすめします。
関連サイト:入札情報速報サービス「NJSS」
③仕様書を確認し、説明会に参加する
入札したい案件が決まったら、詳細が記載された仕様書を確認します。
仕様書はHPに公開されている場合が多いのですが、受け取るためには説明会に参加する必要がある自治体もあるため、必要に応じた対応をしましょう。
仕様書は入札金額を決めるうえで重要な書類となるため、早めの取得と確認が大切です。
なお、入札期日前に入札金額算出に関わる仕様書の内容変更もあり得るため、新しい情報がないかこまめにチェックしておきましょう。
用語解説:仕様書
入札書やその他必要な書類を準備する
公示書と仕様書を確認して入札金額が確定したら、入札書の作成および必要書類を準備します。
自治体によって入札書の様式が異なったり、様式が変更されたりする場合があるため、必ず入札する案件に適合した入札書の作成をしましょう。
また、案件により入札書以外の必要書類は異なるため、「入札説明書」を確認し、入札に必要な手続きや提出書類の詳細、提出方法を確認します。
企業の代表者以外が入札する場合には「委任状」が必須になるため、代理入札の際は忘れず用意してください。
入札は書類に不備があれば失格になるため、十分注意して提出するようにしましょう。
④入札をする
入札期日までにすべての書類をそろえて、実際に入札を行います。
入札方法は以下の3通りです。
- 会場での入札
- 電子入札
- 郵便入札
会場での入札は、指定された会場と時間に、参加者が全員で投票し、その場で落札者が確定する方法です。
一方、電子入札は自治体指定の電子入札サービスを利用して、入札を行います。「〇月〇日〇時〜〇月〇日〇時まで」のように、入札時間が柔軟に設定されていますが、うっかり入札を忘れると失格になるため、早めに入札しましょう。
また、郵便入札は、自治体へ入札書および必要書類を期日までに郵送します。郵便遅延なども踏まえて、郵送はギリギリにならないように注意が必要です。
従来は紙による入札が主流でしたが、業務効率化や透明性向上のため、現在では電子入札への移行が進んでおり、一般化しつつあります。
開札され落札者が決まる
入札が締め切られるといよいよ開札され、各企業の入札金額が公開されます。金額が出そろうと、予定価格に対して最も有利な条件で入札書を入れた企業が落札されます。
一般競争入札では、最低価格落札方式で落札者が選定される傾向にありますが、入札額が最低制限価格を下回っていた場合は失格となり、次に安い価格で入札した企業が落札者となる仕組みです。
入札結果は直接知らされることもありますが、オンラインでの確認も可能です。
ここで自社が落札した場合には、次に発注者との契約になります。
⑤契約をする
自治体と落札者との間で、契約手続きをします。落札日から何日以内と期限が指定されているため、必要書類の準備はスムーズに行いましょう。
契約手続きでは、具体的な業務内容や納期、契約日、金額が記載された契約書が作成され、双方の押印によって契約が成立します。
契約書には業務遂行における重要な内容が記載されています。内容を十分に確認し、不明点の確認や必要に応じた交渉をして、納得したうえで押印するようにしましょう。
入札情報をスムーズに探すなら「NJSS」
入札の発注機関は、国・県・各自治体と多岐にわたるため、自社に合った案件を探すのは時間と労力がかかります。
とくに入札がはじめての企業であれば、案件を探すだけで途方にくれてしまうでしょう。
そんなときは、全国の入札情報がまとめて公開されている「入札情報速報サービスNJSS(エヌジェス)」がおすすめです。
NJSSなら、入札情報の条件を絞り込んで効率的に案件が探せるほか、落札情報からライバル企業の動向調査もできます。
入札案件探しでお困りなら、一度ご相談ください。
入札アカデミーなら入札に関する相談が無料
入札に参加したいが、何からはじめたらいいのかわからない方は、まず「入札アカデミー」にご相談ください。
入札アカデミーでは、プロの入札アドバイザーがマンツーマンでサポートします。
入札経験の有無にかかわらず、現状の課題を整理し、最適な解決策をご提案します。
相談は無料ですので、入札についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
▶ 入札で新しい販路を開拓したい企業の方へ
のべ3,000社以上の相談実績と、NJSS運営16年以上の知見で
入札参入から落札ノウハウまで、入札アドバイザーがサポートします。
▶ 調達業務を効率化したい発注機関担当者の方へ
全国の自治体をはじめ9,000以上の官公庁が公示する調達情報の検索・閲覧が可能。
情報収集・仕様書作成・業者選定など日々の業務を大幅に効率化できます。
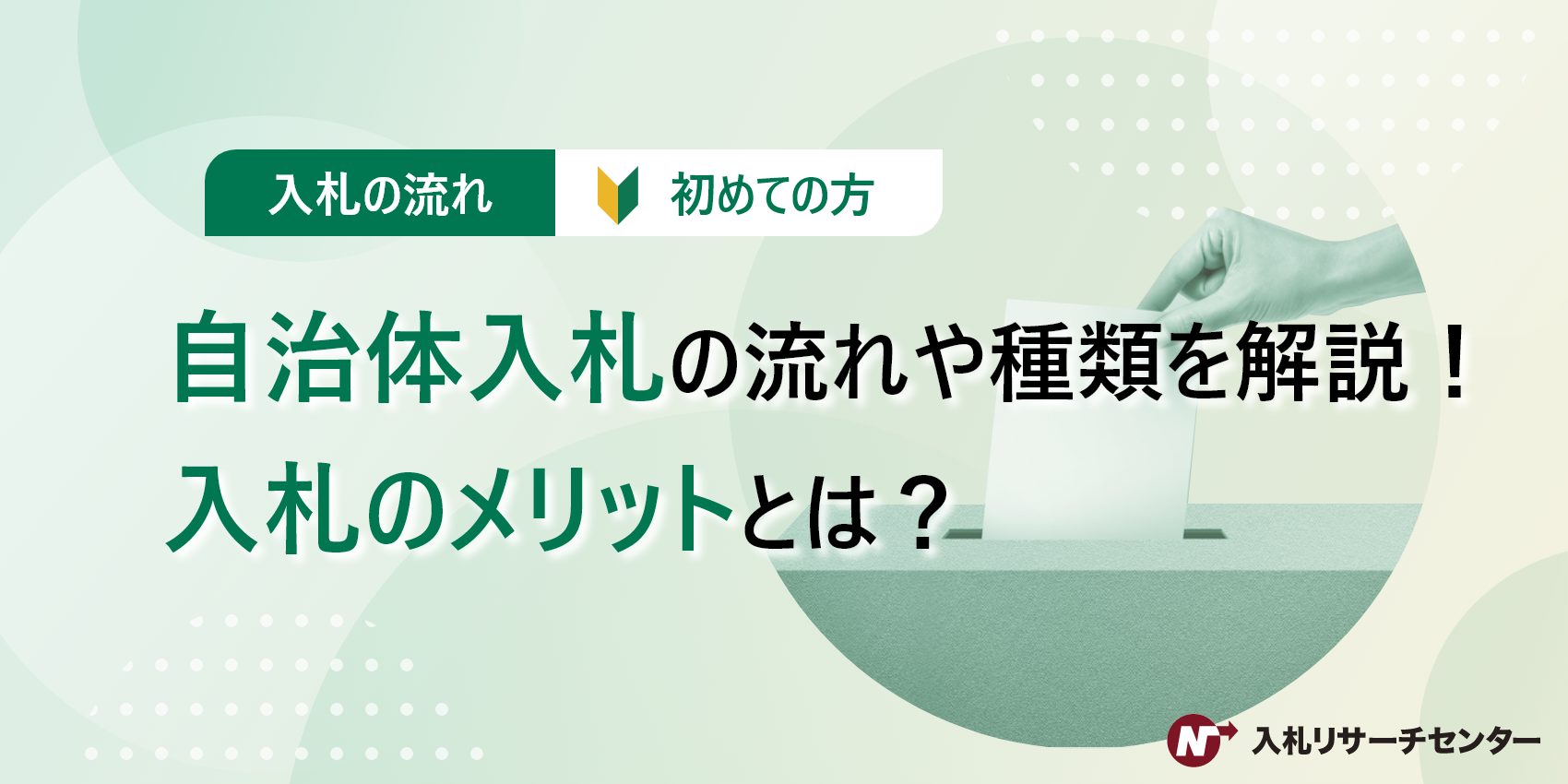
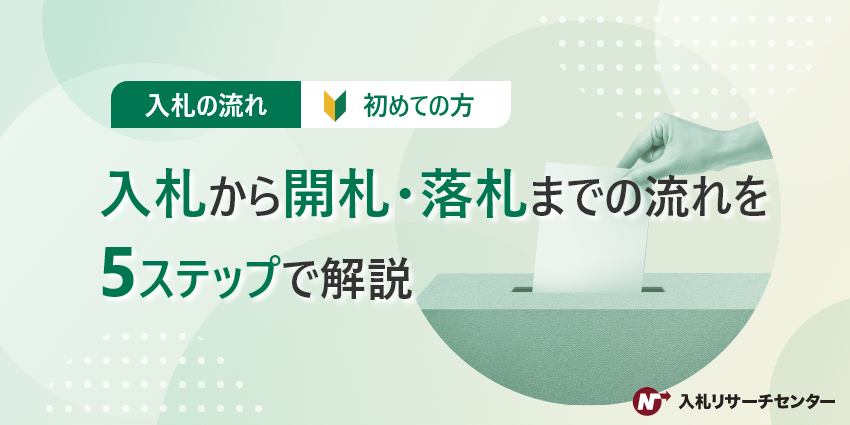

アイキャッチ.png)
.png)
.png)


